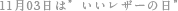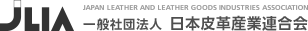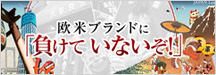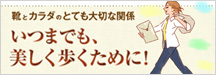March 27, 2019
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」タンナーという仕事には色々あって、それぞれに世界が全然違う、という話
カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」
イベント、セミナーなど精力的に活動する村木さん。皮革に関する確かな見識を有し、幅広い情報発信に支持が寄せられています。
当ブログでは、レザーに関心をもちはじめた若い世代のかたや女性ユーザーにお伝えすべく、わかりやすい解説とともに西日本の皮革産業の現状をご紹介しています。独自の視点・レポートが大好評です。
毎度です! 「ゴージャスでブリリアントでデラックスな革も好き!」な村木です。
今回のお話は、
・タンナーのお祭りに行ってきたのでその報告
・タンナーは鞣しをしているのがタンナー
・仕上げ、という仕事の凄さと面白さ
という話の流れになります。
目次 [hide]
今回のテーマが決まるまでの流れ
で、JLIAさん、ここしばらく続けていた「革製品を作る上での周辺業種の面白さと凄さ」が一段落しましたが、次に何やります? 一応、次の2つを仕込んではいますが。
「靴や鞄メーカーってなんのためにあるの? メーカー飛ばして職人さんとちょくにやり取りすれば商品は安く作れるの?」
「革屋ってなんのためにあるの? タンナーってそもそもなに?」
JLIAさん「そりゃ話してもらいたいのは後者かなぁ」
じゃぁ、前者はその次くらいにしますか。
んと、写真がいくつか必要となりますね。それじゃ姫路でお祭りあるからそれ見に行きがてら写真と証言集めてきましょう。
3/22.23は新喜皮革のレザーフェスティバルが行われていた
2019.3/22.23は新喜皮革さんでレザーフェスティバルが開催されていました。
会期中は新喜皮革のコードバンなども販売されています。あくまでアウトレットセールですね。
私が行ったのは昼過ぎでしたが午前中に革や財布などを求める人が多数来場、昼過ぎからはまったり、とのことでしたが在庫は潤沢に残っていましたね。
「初日のほうが良いの?」と思いますが、2日目も追加で品を入れているので2日目に行っても楽しめるかと思います。
今回会場でfacebookのライブ配信という機能を使ってみました。手持ちのためブレがありますが、会場の雰囲気が伝われば幸いです。
会場内ではチャリティーオークションも開催。鞄や財布などがオークションかけられているなぁ、、と聞き流していたのですが「新喜皮革が鞣したブラックバスの革~」というので慌てて参戦。無事にget。水産革も色々と面白い話が存在しますがまたの機会に。
さて、タンナーってそもそも何?
秋のタンナー見学バスツアーで毎回ご協力頂いているオールマイティーさんを訪れ。
レザー素材オリジナル受注生産|姫路の皮革・革素材/タンナー オールマイティ
ここは革1枚から鞣しをします、というトンデモナイところで、毎回行くたびに変わったものを鞣している。今回は?
オールマイティーさんで見た変わった革
オールマイティーさん「これはな、四国の鹿革なんだけど、オイルをたっぷり含んでくれ、という依頼やねん」
触ってみるとモニョモニョとしたオイルの手触り。べったりとしています。
このスワッチ(材質見本。 見本の小片)から色を再現、っていっても水分とオイルが入って濡れた状態で同じような色合いにできるものなの?
「前回作っているから、きちんと色の処方は置いている。でもそれも原皮(革の元となる皮の状態。今回ならばハンターさんが捌いた毛皮状態でやってくる)の状態によっても変わるからな」
原皮の状態ってのは保存期間とか?
「ちゃうよ。極端な話、餌が豊富な秋と餌がなくなってきている冬では動物の栄養状態が変わるだろ。皮付近の肉や脂ってのは栄養状態でものすごく左右されるから処方をきちんとやっていても元の素材の状態が変わりすぎる。それに応じて処方を変えてやらなきゃいけない。」
大変やん(´・ω・`)
「大変だよ。でもそれが面白いのが革やんか!」
こちらはちょっと変わったもの。オーストリッチ(=ダチョウ)の足ですね。現在の学説では恐竜が進化して鳥になったと言われていますが、これを見ると確かに恐竜っぽいですよね。
ダチョウも日本でダチョウ牧場などで飼育が始まっています。肉も食べるので、革も使うし、足の部分の革も取れるならば使います。さすが最大の鳥類だけあって足まで革として使えます。興味ある方は「オーストレッグ」で調べると販売されているのを見つけられると思います。
これはもしかして、、
「熊の顔の革やな。」
やっぱり、、(゚A゚;) まぁ熊の皮も持ち込まれて革にして、という依頼もあるようで。
鞣しをすると一回り二回りは小さくなりますね。
これは鹿ですね。昨今はジビエなども知られるようになり、鹿肉やイノシシ肉も食べられるようになりました。そうなるともちろん革も使われます。
姫路やたつの市にたまに無茶な質問が来るそうな。
「私達の地方でイノシシ肉や鹿肉を加工して販売している。この革も有効活用したいんだが、自分たちで鞣し加工もしたいのだがどうやるの?」
無茶です(*´∀`)キッパリ
基本的に鞣しという工程は知識と技術と設備、それに大量の水が必要とされる産業です。趣味のものを作るならばまだしも、きちんとした「革」を作ろうと思うと知識、技術、設備、それらを習得する時間と気力が重要となります。
で、それで「確かにそりゃ無理だ!」と思った方がこのオールマイティーさんに持ち込んでくるわけです。
タンナーの定義ってなんだと思う?
オールマイティーさん、JLIA blogでタンナーについて書こうと思うんだけど、タンナーの定義ってなんだと思う?
「大雑把な質問やなぁ~
例えば現在、姫路市、たつの市で130~150ほどのタンナーが稼働している、と言われているけど、俺はそこまで存在しないと思う(※ここらの数字は体感です。登録数は多分もっと多いです)。
それは『あそこのタンナーは実際には動いていないで!』という意味ではなくて、『タンナー』という言葉の定義やな。」
どういうこと?
「タンナー、、、つまりはtannnerやろ?
TAN、ってのは鞣しをする、という意味や。それにerがついて、tannner、タンナーと読むわけや。
ってことは、うちのように大量の水と設備を使って皮から革に鞣しをしているのだけをタンナーというと思う。
でも実際は、鞣しではなくて、染色やスプレー吹きで色付け、型押しや仕上げ加工を得意とする加工所と言われるものも多い。それらは厳密にはタンナーとは言えないと思う。
これは、『鞣しをするタンナーがえらい!』という意味ではないんやで。仕上げ加工をしてくれるところはうちも世話になっているし、そういうところがいないとものすごく困る。ただ、厳密にいえばタンナーとは言いづらいな、と思っとる」
じゃぁ仕上げってなに?
皮革大学というのがある
姫路には兵庫県立工業技術センターの中に皮革工業技術支援センターというものがあります。
で、ここで秋くらいに兵庫県中小企業支援事業の一環で、「皮革大学」というものが今のところは毎年行われています。
これは座学や実技などもありますが、後半には実際に革を鞣す講習も行われます。詳しくは過去に書いたblogをご覧ください。
平成29年度の皮革大学申し込み始まりました。昨年はすごかった。。 | phoenix blog
個人的にはものすごく面白く勉強にはなったのですが、化学用語は飛び交いますので物見遊山で行くとギャフンと驚くことになります。
で、この鞣しを勉強する皮革製造技術部門実習は次のような日程となります。
製革実習 9月 5日間(昼間30 時間)
仕上げ実習 9月 3日間(昼間18 時間)
製革は要は鞣しですね。仕上げ実習は今回説明する「仕上げ」工程となります。
「鞣し」「仕上げ」は設備も考え方も違う
鞣しは毛もついた状態の生々しく塩漬けされた「原皮」を、みなさんが日常で使う革製品で使う「革」にする工程です。
厳密に言うとこの流れはちょっと異なります。順番に見ていくと、、、
塩漬け屋...屠畜場やハンターが剥いだ皮を塩漬けにする工程を行う。
タンナー...皮を大量の水を使い鞣しを行う。革になる。
仕上げ屋...型押し、染色、エナメル加工などを行う
動物からお肉を取り、皮を取った後に、革になるのに最低でもこれだけの会社が関わります。
前出の新喜皮革さんも鞣しを行い、染色までは行いますが、型押しやエナメル加工などは外部の会社にお願いするわけです。それらの工程はそれぞれが専門の高額な設備が必要となり、専門知識が必要となるからです。
仕上げはすごく面白い工程
ムラキ個人は、皮革大学の皮革製造実習で学んで一番面白かったのは「仕上げ」工程でした。
仕上げ工程は「お化粧」だと思ってください。なめされた革の上に様々な化粧=工程をどんどんと載せていく工程です。
で、新喜皮革、オールマイティーの次は、「あれだけ手間かかることはしたくない」と同業他社からも言われるアルファレザーの革をご紹介しましょう
上の写真は、革の鱗1枚1枚にカッティングが施されています。
その上に色を染めています。蛇の模様部分も手作業で塗りの作業を行っています。
塗りの作業を手でひとつひとつ塗ると効率が悪すぎます。そこは特殊な技術が施されているわけです。
柔らかな革の上にハート型で箔押しが行われています。
見てわかりますように広いハートの面の内部がおぼろげに箔が剥がれています。
こちらはハートの縁はきっちりと箔が押され、内部がおぼろげに剥がれるように処理をしなければいけません。この剥がす作業も手作業です。
こちらもギュムっと圧縮してシワが出ています。普通にイメージするような圧縮方法では無理ですね。特殊な機械が必要となります。
こちらは型押しをした後に凸凹で凸の部分だけに染を行い、その上にエナメル加工を行っています。
こちらも型押しですが、凸凹の凸部分に色を載せて、その上にエナメル加工を行っています。
型押し加工には数百種類のパターンが存在し、極論すればそのすべての型押しの凸部分に同じような加工をし、異なる色合いで同じことができるわけです。
他にも様々な加工をアルファレザーさんは手がけています。
もちろん、「私は革らしいナチュラルさが好きなんです!」という人には全く面白くない世界だと思います。ゴージャス!デラックス!ブリリアント!が好き、という人にはものすごく面白い世界です。
仕上げの本質は
私程度の人間が「仕上げの本質はこうだ!」と書くと色々なところから「若造が!」とツッコミが入ってしまうのですが、、、それでも私が思う仕上げの本質とは「こういう加工をお客さんが望む色で、望むパターンで行うことができます」ということです。
元となる土台の革を仕上げ屋さんはタンナーから購入し、その上に様々な仕上げを施します。
土台となる革はキャンパスと同じです。その上にどのような仕上げをするかを考えるのはデザイナーさんなりの仕事であり、それを表現するのは仕上げ屋さんの仕事なわけです。
帰りは革の神様にお参りして
今回紹介した新喜皮革、オールマイティー、アルファレザーは姫路の高木と呼ばれる地域に固まっています。
ここには「高ノ木神社」という革の技術を日本にもたらした神様が祀られている神社も存在します。最後にお参りして帰宅しました。
今後の予定
ムラキが行っているイベント「本日は革日和♪」では、2019.4/5.6は大阪の革屋さん共々イベントを行います。その際に、このアルファレザーさんに来てもらいセミナーというか座談会というかトークショーを行う予定です。
詳しくは下記をご覧ください。
19.4/5.6(金土)の大阪革日和 5日は営業時間延長や展示会など | 本日は革日和♪
4月20.21の土日は東京浅草のA-ROUNDに。こちらはセミナーワークショップ予定。
4月26-28は東京のハンドメイドメーカーズにも出没予定です。
 プロフィール
プロフィール

鈴木清之(SUZUKI, Kiyoyuki)
オンラインライター
東京・下町エリアに生まれ、靴・バッグのファクトリーに囲まれて育つ。文化服装学院ファッション情報科卒業。文化出版局で編集スタッフとして活動後、PR業務開始。日本国内のファクトリーブランドを中心にコミュニケーションを担当。現在、雑誌『装苑』のファッションポータルサイトにおいて、ファッション・インテリア・雑貨などライフスタイル全般をテーマとしたブログを毎日更新中。このほか、発起人となり立ち上げた「デコクロ(デコレーション ユニクロ)部」は、SNSのコミュニティが1,000名を突破。また、書籍『東京おつかいもの手帖』、『フィガロジャポン』“おもたせ”企画への参加など、“おつかいもの愛好家”・”パーソナルギフトプランナー”としても活動中。
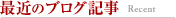 最近のブログ記事
最近のブログ記事
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<9月第2週>
- 【村木るいさん連載】「人に話したくなる革の話」腱鞘炎にならないための考え方とカッターナイフの話
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<8月第4週>
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<8月第2週>
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<8月第1週>
 カテゴリー
カテゴリー
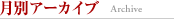 月間アーカイブ
月間アーカイブ
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 4 )
- 2023年7月 ( 4 )
- 2023年6月 ( 4 )
- 2023年5月 ( 4 )
- 2023年4月 ( 4 )
- 2023年3月 ( 5 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年12月 ( 4 )
- 2022年11月 ( 4 )
- 2022年10月 ( 4 )
- 2022年9月 ( 4 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 4 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2022年5月 ( 3 )
- 2022年4月 ( 4 )
- 2022年3月 ( 5 )
- 2022年2月 ( 4 )
- 2022年1月 ( 4 )
- 2021年12月 ( 4 )
- 2021年11月 ( 3 )
- 2021年10月 ( 4 )
- 2021年9月 ( 5 )
- 2021年8月 ( 3 )
- 2021年7月 ( 4 )
- 2021年6月 ( 5 )
- 2021年5月 ( 3 )
- 2021年4月 ( 4 )
- 2021年3月 ( 5 )
- 2021年2月 ( 4 )
- 2021年1月 ( 4 )
- 2020年12月 ( 4 )
- 2020年11月 ( 4 )
- 2020年10月 ( 4 )
- 2020年9月 ( 5 )
- 2020年8月 ( 3 )
- 2020年7月 ( 5 )
- 2020年6月 ( 4 )
- 2020年5月 ( 3 )
- 2020年4月 ( 4 )
- 2020年3月 ( 4 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 4 )
- 2019年12月 ( 4 )
- 2019年11月 ( 4 )
- 2019年10月 ( 5 )
- 2019年9月 ( 4 )
- 2019年8月 ( 3 )
- 2019年7月 ( 5 )
- 2019年6月 ( 4 )
- 2019年5月 ( 4 )
- 2019年4月 ( 4 )
- 2019年3月 ( 4 )
- 2019年2月 ( 4 )
- 2019年1月 ( 4 )
- 2018年12月 ( 4 )
- 2018年11月 ( 4 )
- 2018年10月 ( 5 )
- 2018年9月 ( 4 )
- 2018年8月 ( 4 )
- 2018年7月 ( 4 )
- 2018年6月 ( 4 )
- 2018年5月 ( 5 )
- 2018年4月 ( 4 )
- 2018年3月 ( 4 )
- 2018年2月 ( 4 )
- 2018年1月 ( 4 )
- 2017年12月 ( 4 )
- 2017年11月 ( 5 )
- 2017年10月 ( 4 )
- 2017年9月 ( 4 )
- 2017年8月 ( 4 )
- 2017年7月 ( 4 )
- 2017年6月 ( 4 )
- 2017年5月 ( 4 )
- 2017年4月 ( 4 )
- 2017年3月 ( 5 )
- 2017年2月 ( 4 )
- 2017年1月 ( 3 )
- 2016年12月 ( 4 )
- 2016年11月 ( 5 )
- 2016年10月 ( 4 )
- 2016年9月 ( 4 )
- 2016年8月 ( 4 )
- 2016年7月 ( 4 )
- 2016年6月 ( 5 )
- 2016年5月 ( 3 )
- 2016年4月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 5 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 4 )
- 2015年12月 ( 4 )
- 2015年11月 ( 4 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 5 )
- 2015年8月 ( 3 )
- 2015年7月 ( 5 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 4 )
- 2015年4月 ( 5 )
- 2015年3月 ( 4 )
- 2015年2月 ( 4 )
- 2015年1月 ( 4 )
- 2014年12月 ( 4 )
- 2014年11月 ( 4 )
- 2014年10月 ( 5 )
- 2014年9月 ( 4 )
- 2014年8月 ( 3 )
- 2014年7月 ( 5 )
- 2014年6月 ( 4 )
- 2014年5月 ( 4 )
- 2014年4月 ( 5 )
- 2014年3月 ( 4 )
- 2014年2月 ( 4 )
- 2014年1月 ( 4 )
- 2013年12月 ( 4 )
- 2013年11月 ( 4 )
- 2013年10月 ( 5 )
- 2013年9月 ( 4 )
- 2013年8月 ( 3 )
- 2013年7月 ( 5 )
- 2013年6月 ( 4 )
- 2013年5月 ( 5 )
- 2013年4月 ( 4 )
- 2013年3月 ( 4 )
- 2013年2月 ( 4 )
- 2013年1月 ( 4 )
- 2012年12月 ( 4 )
- 2012年11月 ( 4 )
- 2012年10月 ( 5 )
- 2012年9月 ( 4 )
- 2012年8月 ( 4 )
- 2012年7月 ( 4 )
- 2012年6月 ( 4 )
- 2012年5月 ( 5 )
- 2012年4月 ( 4 )
- 2012年3月 ( 4 )
- 2012年2月 ( 5 )
- 2012年1月 ( 3 )
- 2011年12月 ( 3 )
- 2011年11月 ( 5 )
- 2011年10月 ( 4 )
- 2011年9月 ( 4 )
- 2011年8月 ( 5 )
- 2011年7月 ( 4 )
- 2011年6月 ( 5 )
- 2011年5月 ( 4 )
- 2011年4月 ( 4 )
- 2011年3月 ( 5 )
- 2011年2月 ( 4 )
- 2011年1月 ( 4 )
- 2010年12月 ( 4 )
- 2010年11月 ( 5 )
- 2010年10月 ( 4 )
- 2010年9月 ( 4 )
- 2010年8月 ( 5 )
- 2010年7月 ( 4 )
- 2010年6月 ( 4 )
- 2010年5月 ( 5 )
- 2010年4月 ( 4 )
- 2010年3月 ( 5 )