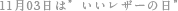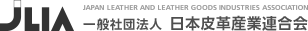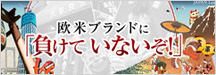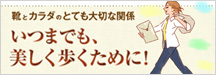カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」 の記事
June 24, 2020
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/姫路市&たつの市のタンナー訪問して いろいろな仕上げ革を見てきた
カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」
都道府県をまたぐ移動の自粛要請 全面解除後、初投稿に相応しい内容です。姫路のイベントのお知らせも必見ですよ。
当ブログでは、レザーに関心をもちはじめた若い世代のかたや女性ユーザーにお伝えすべく、わかりやすい解説とともに西日本の皮革産業の現状をご紹介しています。独自の視点・レポートが大好評です。
人気イベント「本日は革日和♪」。今後の予定、スケジュールなどは下記のリンク先をチェックしてください。
毎度です!
コロナのおかげでお店もさることながらイベントが中止でまぁ大変、です。
自粛解除が出た際に兵庫県姫路市&たつの市のタンナーに行ってきました。
県を越えた移動は自粛を、ということでしたが、幸いにも住まいは兵庫県ですので、県をまたいでいません。( ̄ー ̄)bグッ!
コロナでどう大変だったか
わらじを3足~4足ほど履いているので、村木個人は収入激減などは個人的にはなかったです。
わらじのひとつ、レザークラフトフェニックスはSTAY HOMEの影響か、レザークラフトを始める方が多かったように思えます。そのためネット販売部門は大忙し。
・店頭は自粛期間中は休業にしておりました。
ネットショップは運営していたので、店内ではスタッフがドタバタとしていました。社員・パート・バイト問わず、「出勤時にコロナが怖い」というスタッフには休業補償を支払い、休業してもらっていました。
そんな中、出勤してくれていた社員・パートさんには、「コロナの中出てきてくれてありがとう」ということで500円の昼食補助が支給されていました。
5月21日現在:店頭営業の再開時期についてのご案内 | phoenix blog
・6月に入り自粛解除。店頭は世間が自粛解除しても全面解除は怖い、ということで「月曜~金曜の平日のみ11時~16時まで。水曜定休日。土・日曜臨時休業」という変則的な営業を行っていました。
6月1日より段階的に店頭営業を再開します!まずは時短と曜日の制限ありから。 | phoenix blog
・で、6月15日から通常営業。
6/15(月)より営業時間を通常に戻します。 | phoenix blog
6月23日現在も営業時間は通常通りですが、店内に3組以上のお客がいると2mの距離を保てない、ということで店内入場規制を行っています。
・これらの情報を各種SNS、Blog、グーグルビジネス、などで発信し続けていました。
たまに「どのSNSだけやればいいですか」という質問を受けますが、「お客がやっている可能性がある媒体は全部やるしかねぇ(;´Д`)」というのが回答となります。
ほんとに「遊びじゃねぇんだ、SNSは!」ってなものです。
あ、グーグルビジネスは営業時間修正や定休日変更などがある際は、こまめに変えたほうが良いです。
さて、6月下旬に入りコロナも一段落(第2波怖いが、、) 以前からやりたかったタンナー訪問を開始しました。
なぜこのご時世にたつの市&姫路市に行ってきたのか
毎年11月に兵庫県たつの市で行われているひょうご皮革総合フェア&たつの市皮革まつり。
もう5年〜6年バスツアーをこの日にあわせて決行していますが、個人的に一番の目玉はニューレザーコンテストです。
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/ニューレザーコンテストでタンナーの底力を見てきた、という話を動画で解説しよう | 欧米ブランドに「負けていないぞ !」 | JLIA 日本皮革産業連合会
ここで行われているニューレザーコンテストはタンナーさんが様々な革を出展しています。中には販売用もあるし、到底販売には向かない品などもあります。
で。
このコンテストの上位入賞の革はそれはそれで面白い革も多いのですが、入賞していない革も面白いものが多数存在します。いや、むしろ入賞していない革ほど尖っている革は多いように思えます。
上記の革などは面白い作り方をしているな、と思ったのですが入賞していませんでした。
今回JLIAのblog仕事にかこつけて、タンナーに直接訪れてタンナーを紹介しつつ、どういう作り方やどういう考え方でこの革を作ったか、を聞きたおそうと思います。
姫路市高木のタンナーアルファレザーに挨拶
アルファレザーさんは2年前のニューレザーコンテストで高度加工部門で受賞されたタンナーさん。この革は私は個人的に購入し使っていますが、使ってみてわかる面白い革でした。
で、行ってみると加工の真っ最中。
この革って小さいからカーフ(子牛)、、、にしてはちょっと繊維がゆるい感じがするなぁ。
アルファレザーさん
「これはな、鹿やで。鹿革を預かって
表面加工、その後に
透明フィルムを貼っている最中やね」
透明フィルムを貼ることで汚れ防止や染料の色移り減少にもなります。
この表面にある血筋のような模様は鹿本来が持っているもの?
アルファレザーさん
「いや、これはこちらで模様をつけているんだよ。
印刷じゃなくて手作業で
このように模様をつけることで、
より面白い表情にすることが可能になるんよ」
アルファレザーさんは、仕上げが得意なタンナーであり、この鹿革にしても同業他社さんからの依頼で仕事を行っています。
最近なにかおもしろい革作った?
アルファレザーさん
「もちろんあるで( ´∀`)bグッ!」
こ、これは革の中央にクロコの背中 1本型押し、、、これ、通常のやり方では面倒くさいやり方なのに(;・∀・)
これ、面白い型押し革なんだが、「これを買って鞄にする」よりも「このまま壁に飾る」ほうが見栄えするだろうになぁ。素材としての革ではなくて、インテリアとしての革になる。
※革に型押しする版は畳一畳ほどの大きさがあり、その中にクロコの背中模様が3~4ほど連なっています。そのためこのように1つだけを真ん中に押す、というのはすごく面倒くさく、かつ、嫌がられる。
写真の加減で金色に見えますが、表は金色・裏面は銀色のリバーシブル模様の革となっています。
革は表面の銀面と裏面の床面では繊維の密度が異なります。通常の鞄や財布などは裏面床部分が見えなくなるように布や薄い革を貼る、という工程が必要となります。
この革の面白さは表に金・裏面部分の床に銀にすることで、作業工程の簡略化・軽量化などが可能となります。
ALPHA LEATHER'S GALLERYさんの作品一覧 | ハンドメイドマーケット minne
アルファレザー | LINE Official Account
7月5日に革の市
アルファレザーさんが所属する姫路市高木では、革の里(in ポケットパーク花田)という場所で7月5日に革の市が開催されます。アルファレザーさんもこの日に出店されます。
毎月、第1日曜日に「革の里」構内駐車場において開催される「革の市」。
皮革素材や革製品の販売はもちろん、革の里館内にてキットによるコインケース、ペンケースなどを作れる体験ワークショップも行われます。みなさま、是非ご来場ください。<≪姫路 革の市≫毎月第一日曜日開催 皮革の即売市 - 革の市≪姫路市で毎月開かれる皮革製品、レザークラフト革素材の直売市≫革の里紹介:レザータウン姫路 革の里 レザークラフト教室|財布・靴・革細工|革の市|皮革工場見学 -はりまるしぇ
たつの市のシンヤ工業所へ
※シンヤ工業所さんへは事前にアポを取り、日本皮革産業連合会のblogを書いています、と挨拶してから行っています。普段見学などを受け入れているわけでもありませんので突然訪問!などは絶対にやめて下さい。
シンヤ工業所ってどんなところ?
上記リンク先サイト「日本革市」の説明が丁寧でまとまっています。
HPでもありますように車用の革、クラフト用革、クロム革、グローブ革、ドラムタンニンなど多岐に渡る革を作られています。
タンナーさんは各社によって得意分野が異なります。シンヤ工業所さんの革は、触った限りではコシのある革が得意なように感じられました。
工場は大きく、大勢の人が働いているように感じました。今回訪問した際にはコロナの影響で少し規模を縮小して働いておられました。
ニューレザーコンテストの革を見せてもらった
さて、念願の昨年のニューレザーコンテストの革を見せてもらいました。
この革をコンテストで見て面白いな、と思ったのは「革1枚にこれだけランダムに線が書かれている」のが面白いわけで。例えばA4なりA3 1枚にランダムに線を書くのはそれほど難しくないです。腕を動かしたら描ける大きさはそれほど苦労しません。
ですが、革1枚全体になるとそれを行うだけの場所とその作業をするだけの体力と気力が必要となります。
コンテストでは赤地に黒のみだったのに随分と多色がありますね?
シンヤ工業所さん
「これはサンプルとして
作ったものですね。」
これって、このような模様が存在するわけではなく、実際に筆を使って革1枚に自由自在に書いていますよね?
シンヤ工業所さん
「そうですね。模様がついたプリントも
存在するのですが、
このような模様は存在しません。
ですので、
当社の人間が一人で
このように筆で書きました」
これって、「素晴らしい革だ!じゃぁ鞄で使うから50枚注文!」とか来ると大変じゃないですか
シンヤ工業所さん
「そうですね(;・∀・) 1枚1枚
手で書いていきますので、
作業量が大変です。
あと、この革は割れがあるんですよ」
表面が割れるんですか? プレスか型押しの問題ですか?
シンヤ工業所さん
「いえ、そうではなくて、
この筆で黒い線を書く、という際に
筆の加減で
ボタッと垂れてしまうと、
ダマになってしまいます。
その黒いダマの部分に
厚さが生じてしまい、
曲げると割れることがあるんですよ」
あ~、仕方ないんじゃないですか、それはもう。アヴァンギャルドの代償でしょう。
色々と貴重なお話が伺えました。グローブや車用革などのブレが許されない革を作るシンヤ工業所というタンナーがこれだけブレ幅の広い革をコンテストに出しているのは面白かったですね。
シンヤ工業所様、ありがとうございました!
姫路市御着のレザーカフェに



帰りに、「そういや行ったことなかったな」と思い姫路市御着のレザーカフェに。
ここは御着四郷皮革協同組合が17年9月に作ったスペースです。内容としては御着のタンナーさんの作った革の販売を行っています。レザーカフェ、という名称ですが、カフェ機能は自動販売機によるお茶購入くらいだと思ってください。
なんで飲食業してないの?
レザーカフェさん
「飲食業の許可を得ようと思うと
すごく大変で」
あぁ、保健所の管轄ですからトイレの設置やら、資格やら色々ありますからねぇ。。じゃぁ、この場所のメイン機能は?
レザーカフェさん
「御着のタンナーが作った
革の販売となります」
例えば「この革が次回もほしい」、といった場合は?
レザーカフェさん
「ここで販売しているのは
御着のタンナーが作った
革のサンプル品などになります。
そのためここの在庫のみと
思っていただいたほうが良いですね」
例えば「私はメーカーなので30枚ほしい」とか「定期的に10枚ずつほしい」などの話になると?
レザーカフェさん
「ここは組合が運営しておりますので
『その革ならば~~
タンナーが作っていますので、
紹介します』
ということは可能ですよ」
常設展示場みたいなものですな。下記の革はまたちょっと変わった風合いで面白いですね。





Leather cafe
営業日:月曜日・水曜日・金曜日
営業時間:午後1時30分から午後5時まで
場所:姫路市四郷町山脇150-1 (株)三昌 内
電話番号:080-6219-3403
運営:御着四郷皮革協同組合
※現在コロナの影響で変則的な営業時間となっています。必ず電話してから行ってみてください。
革の仕上げ工程、という面白さ
以前も紹介しましたが、革の仕上げ工程は「革に対するお化粧」みたいなものです。
革のナチュラルな仕上げも面白いのですが、上記にあげたようなアヴァンギャルド、、、一歩間違えば突拍子もない表情も出せるのが革素材というものの懐の深さです。
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」タンナーという仕事には色々あって、それぞれに世界が全然違う、という話 | 欧米ブランドに「負けていないぞ !」 | JLIA 日本皮革産業連合会
革屋さん、という商売は「見た人の4割(6割かな)がほしいと思うんじゃないかな、この革は」「あの会社なら50枚は使いそうだ!」という革じゃないと怖くて仕入れられません。
上記にあるような仕上げ加工の革は、それほど需要が高いというものでもありません。ただ、ほしい人は地球の裏側からでも買いに来てくれる革だと思います。
「じゃぁそういう革はどうやって手に入れたら良いんですか?」 仕上げの革は少数からでも対応可能なものもあります。
「そういうものを実際に見たいならばどうすればいい?」 そこで11月のたつの市皮革まつりのニューレザーコンテストなわけです。ここで革を見て「これ面白い!」と思ったら直接タンナーに相談してみるべきです。
今後予定
6月に入って依頼があり、チラホラと機械の講習や革の講習などに行っていました。
今後は・・・
7月11日(土)・12日(日) 革日和 in 熊本のために会場探しの視察。で、視察だけじゃつまらないのでレザークラフトショップ ANGEL 《熊本レザークラフト教室・革材料販売.革製品販売》にて、革の講習予定。空き状況などはレザークラフトショップANGELさんにお問い合わせください。
7月19日(日) 7月19日(日)教えるフェスタ2020《11人の数珠つなぎライヴ配信》 | サンプル師が教えるバッグ教室参加
10月2日(金)・3日(土) ジャパンレザーアワード(現在、事前エントリースタート)審査会にて革日和出展予定
カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」
レザークラフト初心者向けのセミナー、ワークショップを数多く開催してきた村木さんならではのレクチャーは、とても詳しくわかりやすい内容。さらに、レザーケアのエキスパート、いちかわたかおさんにインタビュー。withコロナ時代のニューノーマルともなりえる、お手入れ&ウイルス対策をまとめてご紹介!ぜひ、参考になさってください。
当ブログでは、レザーに関心をもちはじめた若い世代のかたや女性ユーザーにお伝えすべく、わかりやすい解説とともに西日本の皮革産業の現状をご紹介しています。独自の視点・レポートが大好評です。
<http://ccrui.sakura.ne.jp/kawabiyori/>
毎度です!「今後100年にわたって2020年はすごかった、って言われるんだろうな」と思っているムラキです。
まぁ、コロナでこう大変だ、などの記録記憶は他の人におまかせしておいて。
今回の騒動を機に、「家でやる趣味としてレザークラフトはどうだろう。いくら位かかるの?どこまで作れるの?」「革の手入れをやろうと思うがそもそもなんで手入れがいるんだよ?革は不便なのか」というような質問を見たり聞いたりしました。
今回のblogでは、これらの質問に軽く答えてみようと思います。
さらに、「コロナ時代の革の手入れはどうやるか」という話も書いておきます。
*
目次 [hide]
レザークラフトをやってみたい!という人向けの話
最初に聞きたい!いくらかかるの?
レザークラフトって面白いの?
道具は何を買えばいい?
材料はどう買えばいい?
動画で学べる?本はどう?
レザークラフトでぶつかる最初の壁は騒音対策
革製品のお手入れって大変そう。でもやってみたい、という人向けの話
そもそも革製品の手入れってなんでやらなきゃいけないの?
これ一つで全部の革製品をケア出来る、という魔法の品はない
革靴ならば日常でこの程度やっておくだけでも違います
革鞄ならば日常でこの程度やっておくだけでも違います
革財布ならば日常でこの程度気を使うだけで違います
withコロナという時代の革製品手入れ
ビフォーケアという考え方
withコロナ時代の革製品のケアの考え方
*
レザークラフトをやってみたい!という人向けの話
最初に聞きたい!いくらかかるの?
大阪のフェニックス店頭でよく聞かれたのがこの質問です。で、回答は「道具代金が最低限で6000円くらい。ブックカバーかパスケース作るくらいの革を買って3000円くらい。参考の本を買って3000円弱くらい。1万2000円くらいですかね。」というものでした。これが私が店頭に立っていた頃だから、、、もう6年くらい前かな?
今ならば「参考の本を買わずにYouTube見てやってみましょう」となるので、参考の本を抜いて1万円くらいですね。
レザークラフトって面白いの?
面白いですよ!
自分で財布なり鞄なりの実用的なものも作れますし、日常生活でちょっとあればいいな、と思うものも作れます。
でもミシンとか使ったことないよ?
>手縫いの場合は手作業で穴を開けていきます。ミシンなんていりませんよ。
道具は何を買えばいい?
「人に話したくなる革の話セミナー・革の買い方や歴史編」で配る工具リストがあります。最初にこれだけ買っておきなさい、というものですが、写真付きで解説してみましょう。
菱目打ち
フォークのおばけみたいな刃物です。これで糸が通る穴をあけていく、という工具でこれがなければ話になりません。日本ではクラフト社・SEIWA・協進エルの3社が主に国産の菱目打ちを販売しています。SEIWAと協進エルは同じものを販売していますので実質2種ですね。
どちらのほうが良いの?
>どちらも大差はないです。購入する時に「自分は、クラフト社の4mm幅を購入した」などきちんと覚えておいてください。「以前どちらの種類買ったか思い出せない」というケースは店頭でよく聞きましたので。
某巨大販売サイトで外国製のものが安く売っているがこれじゃ駄目なの?
>オススメしません。なんでもかんでも国産最高!というつもりはないですが、これに関しては上記3社が販売しているものをオススメします。
最初にどれ買っておけばいいの?
>2本菱目打ちと4本菱目打ちを買っておいてください。この2本があれば直線も曲線も縫えます。
ゴム板
菱目打ちで穴をあける際の土台となります。
いろいろな大きさがあるけどどれがいいの?
>大は小を兼ね、という品ですので大きくて分厚いもののほうがオススメです。
100均で売っているゴムのまな板とかじゃ駄目?
>薄くて使いづらいです、あれ。
木槌
金属ハンマーでも良いのですが、使っていくうちに徐々に工具を痛めてしまいます。木槌のほうがオススメですが、ホームセンターのゴムハンマーなどでも構いません。ゴムハンマーですと威力は4割へるけど、騒音は5割静かになります。
木槌がすごくオススメ、というのは過去のblogで紹介していますので、またご覧ください。
1500円程度の投資で効率が3倍良くなるのが実感出来る太鼓木槌 | phoenix blog
革を切る工具
革包丁、というものを使いますが、最初はこれを買うのはオススメしません。理由は3つ。
1 研ぎをこまめにしないと意味がない。購入時に砥石購入必須
2 慣れるまで使いづらい
3 最初に買うにはちょっと高い(4000円弱します)。
それならば、カッターナイフをこまめにポキポキ折りつつ作業することをオススメします。
OLFAさんが革たち、という革包丁の形をしたカッターナイフ的なものも販売しているのでこちらもオススメです。
研ぎ、という工程はこれ単体で趣味になるほど奥深い技術です。この研ぎを怠けて革包丁を使うと、「あれ?切りづらいな。力を入れよう」>指をザクッ!となることもありえます。最初はカッターナイフで十分です。
糸・蜜蝋
革を縫う糸は麻糸を一般的に使います。糸の撚り(より)がミシン糸と逆方向になってしまいますので、手持ちのミシン糸では縫えないと思ってください。
蜜蝋は糸に粘着力を与えるために使用します。
仏壇に置いてあるろうそくじゃ駄目なの?
>駄目です。滑りがよくなって逆効果です。
接着剤
縫う前の仮止めとして使います。基本的に「接着だけで永遠にくっついてくれる」という魔法みたいな接着剤は存在しません。接着剤はどれだけ強力なものを使おうとも、どれだけきちんと使い方を守ったとしても、必ず、いつかは、剥がれます。だから接着剤はあくまで仮止めとして使います。
様々な種類が存在しますが、100均でも売っているG17なり革もくっつく接着剤でも十分です。
使い方は?
>革をくっつける接着剤は、「両面に塗って乾燥後にくっつける」というちょっと変わった使い方をします。購入時に説明書をじっくり読んでください。
ディバイダー
革を縫うために菱目打ちで穴をあけます。その穴を開けるために革の表面に線を引くのがディバイダーという工具です。
いつかは必ず買いますが、最初に買わなくてもいいです。2本菱目打ちで代用も可能です。2回なにか作品を作れば「ディバイダーという工具があるそうだが、買ったほうが便利そうだな」とわかるかと思います。
カッターマット
革を切るときの作業台として使います。100均でも良いのですが、せめて700円程度出して最低でもA4サイズを使ってください。作業スペースの大きさは作業効率に繋がります。失敗しないためにもぜひカッターマットを買っておいてください。
材料はどう買えばいい?
革素材の厄介な点は以前も説明していますが、お腹や背中では強度や品質に大きく差異が生じます。また、年月を経た革素材は油分・水分が切れてカサカサとなり、強度も著しく落ちます。
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」良い革の定義は難しい・悪い革の定義は簡単 | | JLIA 日本皮革産業連合会
格安の端切れ革などは、この年月を経たためにカサついたものも見受けられます。ですので、買うならば革屋さんで定番の品がオススメです。
「自分の県内には革屋さんがない」「東急ハンズもない」などの声もよく聞きますが、そもそも革屋さん自体がそんなにありふれたお店ではありません(´・ω・`) 。東急ハンズもクラフトコーナーを持たない店舗も増えています。
で、やっぱりネットで購入が手軽ではあります。
どこの店が良い・悪い、とは言えないです。JLIAのblogで特定の店を「ここ良いよ!」「ここイマイチだよ!」とか書くわけにはいきませんので。(あ、私も関わっているレザークラフトフェニックス、よろしくおねがいします!)
メルカリなりヤフオクで端切れ革の販売もありますが、長い年月を経た革は強度も悪く作成しづらいです。お腹部分・首まわり部分などは線維がゆるいため、こちらも作成しづらいです。
「自分は始めたばかりだからそれでいいや」と思いがちですが、あまりに線維がゆるいものはきれいに作れず、「この程度しかできないならやめよう」と思いがちです。「端切れなどの革を大きいサイズ買う」ではなく「切り売りなりA4サイズの革を買う」ほうが初心者には使い勝手が良いと思います。
動画で学べる?本はどう?
動画で学べますね、今の時代は。便利な時代だなぁ。YouTubeでレザークラフトなりで検索すれば色々と出てきます。
型紙がほしい、という場合は本を1冊購入をオススメします。大型書店などに行けばレザークラフトの本も数冊くらいは置いています。図書館ならば5冊くらいは今の時代置いています。
最近は動画からはじめました、という人も多いですし、本も私が学んだ時代に比べると数十冊出版されています。下記のスタジオタッククリエイティブは1つの出版社ながら数十冊出版しています。下記サイトでわかりやすくそれぞれの本が解説されています。
STUDIO TAC CREATIVE レザークラフト
>STUDIO TAC CREATIVE レザークラフト LEATHER CRAFY BASIC SMALL ARTICLES & BAGS レザークラフトベーシック 小物&バッグ編
最初はきれいに出来ないでしょ?
それはもちろんです( ´∀`)bグッ!
最初からきれいに作りたい!という方は教室やワークショップにいくことをオススメします。
下記サイトは、レザークラフトフェニックスに投稿されたお客さんの作品一覧です。
見てみるとわかりますが、作って1年未満という方も多いですよ。やっていたらうまくなります( ´∀`)bグッ!
レザークラフトでぶつかる最初の壁は騒音対策
レザークラフトを始めた人が必ずぶつかる壁が騒音対策です。
革に穴をあける工程で、ドンドンという振動が地面に伝わります。マンション・アパートですと確実に階下から苦情がきます。知り合いは、「駐車場や公園でこっそりと穴だけ開けて慌てて家に帰っているよ」という証言をしていました。
で、オススメは下記blogで紹介している方法。太ももの上に木を置いてその上で作業する、というものです。私自身この方法でマンションで作業しましたが苦情はなかったです。
動画で見よう!音と振動対策:ケヤキの塊を足の上に | phoenix blog
革製品のお手入れって大変そう。でもやってみたい、という人向けの話
そもそも革製品の手入れってなんでやらなきゃいけないの?
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」良い革の定義は難しい・悪い革の定義は簡単 | | JLIA 日本皮革産業連合会
上記blogでも解説していますが、長い年月放置した革は油分・水分が切れてしまいカサカサになります。
人間もお風呂上がりに乳液をパックして保湿しないと、肌はカサカサになっていきます。革の手入れも同じです。
これ一つで全部の革製品をケア出来る、という魔法の品はない
革製品といっても靴・鞄・財布ではダメージを受ける部分、ダメージの種類などが異なります。そのため「これだけやっていたら十分!」「この製品で全部ケアできます!」ということはありえません。
なにかしらのブランド品ならば、購入店舗で「お手入れはどうしたら良いですか?」と聞くのが一番です。
お手入れ商品が売っているお店で購入しよう!という場合は、実際にケアする品を持っていって店員さんに聞いてください。店員さんいわく「実際の商品なしに~~のブランドの革財布をケアするにはどれを使えば良いんですか、とか、ブーツケアにはどのクリームが良いんですか、と聞かれても実物見ないと判断できないんですよ」とのことです。
革靴ならば日常でこの程度やっておくだけでも違います
革靴ならば靴用ブラシ(数百円)を購入し、数日に一度ホコリをはらっておくだけでも違います。
靴の場合は、甲部分と底部分の接合部などに汚れが溜まりやすいので重点的にホコリをはらってあげてください。
日本で革製品を使う上で恐れるのはカビです。特にこれからの時期は湿度が高まりカビやすくなります。
除湿剤などを靴に入れておくと、袋から除湿剤が漏れて革に付着すると革にダメージが起こりえますのでお気をつけください。
靴の形をした木製のシューキーパーは、靴の型崩れ防止と湿気取りという役割があります。大事な靴の場合は数日に一度シューキーパーを付けるのも手です。
きちんと手入れをしてみたい!と思ったら下記を見てみてください。スターターセットの宣伝ではあるんですが、コロンブスさんのお手入れ動画などもまとまっています。
【前編】靴をキレイにしてみよう!初心者さんへもオススメのスターターセット。 | phoenix blog
革鞄ならば日常でこの程度やっておくだけでも違います
定期的に中の荷物を出してホコリを払ってあげてください。毎日掃除する必要はないですが、数週間に一度は行ったほうが良いです。
雨で濡れた場合などは、100均で買える洗濯ネットなどに新聞紙を入れたものを革鞄の中に詰めてください。型崩れ防止になります。濡れた革製品は日陰でゆっくりと乾燥させてください。天日干しをしてしまうと革が痛みます。
革の鞄はクリームやオイルでケアしますが、マチ部分などの細かい可動部分のケアを忘れがちです。この部分は一番良く動くのでケアを忘れないようにしましょう。
革財布ならば日常でこの程度気を使うだけで違います
基本は革の鞄と同じです。財布もマチ部分のケアを忘れられがちですね。
普段革小物作っている立場として言うならば、「カード入れ部分にカード4枚とか入れないでください」です。クレジットカードなどの厚いプラスチックカードはカード入れ部分に3枚以上入れると確実にダメージになります。
withコロナという時代の革製品手入れ
レザーソムリエ講座で革製品のお手入れ解説をしてくれている いちかわさん、今度JLIAblogで初心者向けの革製品の手入れの話書くけど、なにか他にネタないですか?
いちかわさん「手入れのこと書くの?それじゃビフォーケアとコロナ対策の話も入れといてよ」
ということで下記からはケアのプロフェッショナル、いちかわ氏の解説です。
ビフォーケアという考え方
革製品の手入れは、製品の使用後に行うものと思っている人が多いですが、革製品は使いながら完成させていく製品です。買ったときは、まだ完成してないと考えてください。
ですから、手に入れたら まず 「お手入れ」をしましょう。製品を使う前のケア=ビフォーケア、という考え方ですね。これを行うことで、長く自分だけのより良い持ち物にしましょう。
- 「お手入れ」知識としては、クリーナー(汚れ落とし)の使い方を知ることが一番です。これを知ると持っている革が何に弱いかがわかります。
- 普段の「お手入れ」の目的は、製品の点検です。キズ、色落ち、色剥げは、革の致命傷になることがあります。早く見つけることが必要です。傷を見つけた場合は修理店などに相談してみましょう。
- クリームは、革のサプリです。不足している水分、油を補います。水分、油が適正ですと、革は強さを保てます。
withコロナ時代の革製品のケアの考え方

厚労省と国立感染症研究所の発表ですと、コロナウイルスは表面を油膜で保護されています。この油膜を取ると死にます。
そこで、アルコール(高濃度)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤が有効であると推奨されています。
では、革製品にこれらは、使えるでしょうか。
アルコール(高濃度)、次亜塩素酸ナトリウムを革製品に使ってはいけない!
アルコールは、革の塗料を溶かすことがあります。
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/コロナウィルスと革製品の話
次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性です。アルカリはタンパク質に影響します。
この2成分が含まれているものは革に使ってはいけません。
使うならば中性の界面活性剤があるものを。
界面活性剤は、石鹸に含まれていますが、これが革につかえます。ただし、石鹸は普通アルカリ性です。今は、中性洗剤ができています。もし汚れ落としに使う、というならば中性のものを使いましょう。
市販されている乳化性クリーム(瓶入り)、革用クリーナー、ローションは中性タイプが多く、界面活性剤を含んでいます。
アルコールのように高濃度でなくても効果があるそうです。また、ニューヨーク病院の報告ですと、靴底がウイルスを運ぶとあります。靴底には、液体のクリーナー、ローションを塗れば良いでしょう。
ブラシのホコリ落としは要注意!
「お手入れ」は、普通ブラッシングから始めますが、ホコリと一緒にコロナも空気中にでるので、ここでは順番を変えて、液体のクリーナーなどを布にとり靴を湿らしてから始めましょう。
水分を与えることでコロナウィルスが空気中に飛散するのを防ぎます。
これだけ気を使っていても必ず換気の良いところで手入れをしましょう。
「お手入れ」中は、必ずマスクをしましょう。メガネ、ゴーグルもできれば。終わりましたら、手は、必ず丁寧に洗いましょう。
コロナウィルスは手に付着しても口目鼻などを触らない限りは安全です。ただこのウィルスがどこにあるかはわかりません。靴は地面に落ちているウィルスが付着している可能性がありますので、手などに付着しないように気をつけましょう。
April 22, 2020
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/オンライン飲み会と配信をやってみてわかったこと
カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」
なお、大型連休中の更新はお休みとなります。次回は5月13日更新予定です。ご了承ください。
当ブログでは、レザーに関心をもちはじめた若い世代のかたや女性ユーザーにお伝えすべく、わかりやすい解説とともに西日本の皮革産業の現状をご紹介しています。独自の視点・レポートが大好評です。
<http://ccrui.sakura.ne.jp/kawabiyori/>
* * *
毎度です!「目に見えない宇宙人から侵略戦争受けているようなものだな」と思っているムラキです。
SFの世界ですね。
さて、今月も辛気臭いコロナの話になりそうですが、身の回りの話からしてみましょう。
大丈夫!
「はいはい、景気悪いよね!」と辛気臭い内容にはしませんので。
*目次
レザークラフトフェニックスは実店舗自粛休業中
フェニックスのコロナ対応
なぜここまでやっているか
これらの対応を各種SNSで告知している
で、面白いことしようと思ったのでオンライン飲み会をライブ配信しようと思った
選んだツール:オンライン飲み会サイト「たくのむ」「whereby」
選ばなかったツール:オンライン飲み会では下記を選択肢から外しました。
選んだツール:配信ソフト Open Broadcaster Software | OBS OBS
選んでよかったもの・用意しておきゃよかったもの
で、なぜ失敗したか
事前にオンライン飲み会を数回やってみた
どういう失敗だったか
で、失敗原因
やった価値あるの?
SNSや再生回数よりも重要なのは信頼の深度
オンライン飲み会のライブ配信は結構難しい
質問と回答
今だからこそ、新しいことをやりやすい
大阪近辺の話
私が働いている難波近辺は関西空港からの玄関口である南海電車なんば駅があります。さらに民泊特区にも指定されている地域のため、コロナ以前はスーツケースをガラガラと引っ張っている外国人観光客さんがいっぱいでした。
で、現在はそういう方をさっぱり見かけなくなりました。
大阪らしい風景と言える道頓堀のグリコ近辺の写真でも平日昼間はこの様相です。
レザークラフトフェニックスは
実店舗自粛休業中
私が関わっているレザークラフトフェニックスは、現在緊急事態宣言を受けて実店舗を自粛休業・ネットショップは通常営業となっています。
フェニックスのコロナ対応
この休業ですが、事前にルールを決めていました。緊急事態宣言が出たら店舗を閉めます。
スタッフに陽性感染者が出たら~~します、など決めておき、4/6に発表していました。
新型コロナウイルス感染拡大による今後の営業についてのお知らせとお願い | phoenix blog
社長と社員が相談していたおかげで緊急事態宣言が出た際も慌てずに体制を整えられました。
【重要】店頭営業自粛のお知らせ | phoenix blog
この体制が続いた場合や、「店頭で受け取り可能?」などの質問集をまとめて告知しています。下記blogは追加の質問があれば随時更新するようにしています。
新型コロナウィルスに対して当社対応の質問回答一覧 店頭受け取りの方法や、更に自粛する場合の解説など。 | phoenix blog
フェニックスではパート社員問わず、休業補償を出しています。「家庭で高齢の方がいる、などで外に出たくない、という場合でも遠慮なく言ってください。きちんと休業補償を出します」と最初から言っていました。
フェニックスのみならず、関西の革問屋さん・モノづくりの材料店なども分かる範囲で更新し、情報を整理してまとめました。
関西の革屋さん・関係店舗の新型コロナによる営業変更一覧 | phoenix blog
また、スタッフさんがSTAYHOMEということで、初心者の方向けのレザークラフト制作blogをあげてくれました。
【型紙付き】自宅待機の人は、革のハギレで"使えるアクセサリーマット"を作ろう | phoenix blog
【型紙付き】あまりにもマスクが売ってないので革で作ってみたよ。 | phoenix blog
なぜここまでやっているか
材料店舗、というのはモノづくりをする方にとってのインフラです。特にフェニックスの場合はお客さんが持っている革を薄くする=漉きの受付もやっているため、かんたんに休むわけにはいきません。
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」 革を薄くする仕事「漉き割り」の世界 | 欧米ブランドに「負けていないぞ !」 | JLIA 日本皮革産業連合会
その一方で働いている
社員さん、パートさんも大事です。すごく大事です。
ですので「こうなると休みます、というルールをきちんと最初に告知しておきます。だから、お客さん、見ていてください。いつ閉まるかわかりませんので注文はお早めに」という体制を作っています。
「閉まらないのがお客さんへのサービス!」ではなくて、「こういうルールで閉まりますので、お客さんもそれを考慮して動いてくださいね」と考えています。
一番駄目なのは突然閉まること・閉店するだと思っていますので。
これらの対応を
各種SNSで告知している
ルール作りも重要ですが、ここから更に告知をきちんとしました。どれだけ面白いこと・新しいこと・良いことをしても、知ってもらいたい層に情報を届けないと意味がありませんので。
各種SNS=インスタグラム・Twiter・Facebookでの告知はもちろんやりました。
結構重要なのはGoogleです。Googleで「レザークラフトフェニックス」と検索したときに出る情報で「臨時休業中」「コロナ対応でこうやっています」などの情報を載せるようにしています。
革業界でGoogleマップやGoogle検索した際に出るこのGoogleビジネスをきちんとやっているところは少ないですが、ここはきちんとやっておいたほうがいいです。
営業時間や近況などを更新しておくだけで十分です。
HPは作っておいたほうがいいのは当たり前ですが、このGoogleビジネスを疎かにしておくと、10年単位で先々エライことになります。(エライことになる、ってのは関西弁で「大変な事態になりますよ」という意味ですわ┐(´д`)┌)
SNSをまめに更新、なんてことよりも先にこちらをきっちりをオススメします。どうせ始めた当初のSNSなんて誰もみませんが、Google検索は多くの人が見る可能性ありますので。
で、面白いことしようと思ったので
オンライン飲み会をライブ配信しようと思った
結論から言うと失敗しました。で、失敗のほうが学ぶこと多いので色々書いておきましょう。
失敗経験のほうが聞いていて面白いですからね (ヽ´ω`)
目的
オンライン上で飲み会をしている風景をオンラインで配信する。見ている人がそれを見てツッコミを入れて、飲み会をしている人間が答える。
手段
オンライン飲み会サイトをYou Tubeでライブ配信
順番に解説していきましょう。

選んだツール:オンライン飲み会サイト「たくのむ」「whereby」
2020/04月現在、「多人数がオンライン上で会議する・飲み会をする」というツールは増えてました。
それこそスマホでLineなりSkypeなりで複数人でのTV電話状態にしておき、スマホを置いて飲み会なり会議すればいいだけです。
今回のオンライン飲み会ライブ配信ですが、1回こっきりではなく、今後継続するつもりです。それも同じメンツではなく、毎回人を変えていこうと思っています。
そうすれば普段表に出ないタンナーさんや加工屋さん、メーカーさんなども表舞台に引っ張り出せますので(´・ω・`)
で、
その際に「これをやるためにこのアプリを入れてくださいね」「ノートパソコンにこのソフト入れてくださいね」などの手間暇を他の人にやらせたくありませんでした。
最初に試した際はスマホの使い方が詳しい人が協力してくれましたが、今後そこらが詳しくない人とオンライン飲み会をする可能性も高いです。そうなると「アプリ入れて」「ソフト入れて、ここをクリックして」などの手間暇を少なくしたかった。
選んだのが下記2サイト
オンライン飲み会サービス『たくのむ』
無料でオンラインルームを作れる。7人以上有料だが、現在12人マックスで無料。現在はID・パス不要
Video Meetings, Video Conferencing and Screen Sharing | Whereby
海外サイト。上記たくのむ、と機能はほぼ一緒。5人以上有料。
機能はほんとにほぼ同じです。
これら2つはオンライン飲み会・会議をする「ルーム」を作ると、そのURLを相手に送るだけで参加が可能、という手軽さです。
「たくのむ」は日本語のため、相手が安心感があります。ですが、金土の夜などは参加者が多いらしくアクセス不能となります。
「whereby」は海外サイト。登録にIDなり、fbやgoogleアカウントがいります。ですが、サーバーが強いのか、時差の影響か、金土でも軽く繋がります。
これら2つを使うことでオンライン飲み会が可能となります。
選ばなかったツール:オンライン飲み会では下記を選択肢から外しました。
今現在、zoomというオンライン会議ソフトが流行です。これは使い勝手が良いことはわかっているのですが、ちょっとよろしくない噂も多いので正直使いたくない。(ムラキ個人の考え方・感想です。使おうと思うと使い手にセキュリティ意識がないと、大火傷しかねない箇所がありますので怖いんですよ)
セキュリティ高めて用心していたら問題ないかな、と思っているのでまた試してみます。
chatworkやlineも、「相手のスマホにこれを入れてアカウント作ってね」という手間がかかるため選択肢から外しました。
選んだツール:配信ソフト Open Broadcaster Software | OBS OBS
Open Broadcaster Software | OBS
ライブ配信をする、というのならば最初の一歩ならばこれ。フリーソフトです。
「PCでたくのむでオンライン飲み会をしている風景を映し、その風景をそのままYou Tubeライブ配信」という環境で行いました。
選んでよかったもの・
用意しておきゃよかったもの
・「spacedesk」というソフトで手持ちのタブレットをノートパソコンのサブディスプレイにしておいた
紹介blog>「spacedesk」でマルチディスプレイが無料で高性能、超簡単。タブレット、スマホ、ノートPCが外部画面に。 | Cloud-Work | 生産性向上
「ノートパソコンの画面をそのまま配信」というのは良いのですが、配信ソフトもチェックしなければなりません。
ってことは「配信用の画面」+「配信ソフトOBSをチェックする画面」と2つがいります。1つのノートパソコンの画面で2つをチェックするのはめんどくさいので却下です。
HDMIでサブモニタをつなげばいいから、サブモニタ購入するか、2万円くらいのを、と思いましたが、「手持ちのタブレットをサブにできねぇかな?」と調べたら上記のアプリ・ソフトが。
無線でつながって便利ですが、0.5秒ほど動作が遅くなります。まぁ、たくのむサイトを表示したままにするためですから問題なし、です。
タブレット・スマホを何台でもサブディスプレイにできます。便利ですよ、これ。
・マイク
ノートパソコンにwebカメラとマイクは付いているのですが、マイクの性能がしょぼかったかな、と思います。安いのでいいから口元にほしいですね。
で、なぜ失敗したか
事前にオンライン飲み会を数回やってみた
数回はオンライン飲み会を友人とやってみました。
・wifi環境が太くないと動画・音声が止まる
・4人くらいが限度かな。
・相手の話の切れ目がわかりづらい
・他の人が喋りだすタイミングがわかりづらく、質問が被ることがある=質問したい人は挙手のスタンプを押す、などのルールがいるかな
・手酌で飲むので気づくと量が、、、、
などを学んでおきました。
1回はYou Tubeライブ配信もこっそりと非公開でやっており、映像も大丈夫、とわかっていました。
で、結果的に大失敗 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
どういう失敗だったか

左上が私、右上がフェニックススタッフ仲地、下が香川の刃型屋さん。
で、私の声だけが聞こえない、という状況でした。1時間中40分ほど私の声が無音or聞こえづらい (;´Д`)
原因解明に時間を要しました。オンライン飲み会しつつ、手元で原因を調べまくります。
で、失敗原因
・自宅のwifi回線が細かった
有線でつないだほうが回線は安定しますね。
・たくのむ も混んでいた
オンライン飲み会サイト「たくのむ」ですが、リリースがつい最近です。今の時代でオンライン飲み会が増えたため、急激なユーザー数とサーバーの太さが釣り合ってないように思えます。
21時スタート、という飲み会が多くなる時間だったのも失敗だったかな、と。20時とか21時ならばwherebyのほうが良いかもしれませんね。
あ、たくのむは面白い使い方ができそうな気もしますので皆さんぜひ使ってみてください。オンライン会議なども手軽にできますよ。zoomと違って無料で使っても時間制限ありません。
・You Tubeのコメント欄を見るのが無理だった
ノートパソコンで配信ソフトOBSを見つつ、タブレットでたくのむ表示。
これ、実際にYou Tubeできちんと音が出ているかどうか、とか、コメント欄を見る余裕がないんですよね。
スマホのほうでYou Tubeを見るのも可能なのですが、ハウリングおこすのであまり繋げたくなかったんです。これも失敗理由の一つでした。(;・∀・)
一緒に飲んでいた仲地さんがYou Tubeのコメント欄を読んで「あ、これは質問だな」と判断してオンライン飲み会で「いま、こういう質問来ていますよ」「音聞こえない!と言われていますよ!」という流れができたのは良かったですね。
一人でも全部やろうと思ったらサブディスプレイ3台はほしいですね。でも助けてくれる人はしみじみ「力」だな、と思いましたわ
・配信ソフトのOBSの設定が間違っていた
もう単純に設定ミスです。設定>音声で選ばれていたマイクが違うものでした。
私の声だけ聞こえない=他の人は聞こえている>ってことは、たくのむ・You Tubeが悪いわけじゃない。
私の環境の問題>回線か?ノートパソコンか?と思考を張り巡らしますが、ここで「動画は動いていて音がでないならばマイクの問題」と即座に気づけませんでした。
こういうパソコンやネット系のトラブルは「原因発見9割、解決時間1割」です。気づけばすぐに解決なんですけど、今回は「たくのむ」「OBS」「You Tube」と3つを介して行っていたので原因追求に時間がかかりました。(ヽ´ω`)
やった価値あるの?
ありますね、確実に。
SNSや再生回数よりも重要なのは
信頼の深度
私はSNSのフォロー数やYou Tubeの視聴回数や登録者数、blogの閲覧数を競うのはあまり意味がないと思っています。
そこらあたりが直接収入に結びつく商売もあるのですが、私のような仕事の戦い方では数を競う意味はないです。You Tubeでお金もらうのって1回の再生数で10万とか超えないと無理ですよ┐(´д`)┌[
重要なのは信頼です。
「この人の言うことは面白い」「信用しよう」と思ってもらうための手段がSNSやYou Tubeなりblogなわけです。
SNSはどうしても短期決戦のツールです。それに対して動画やblogは長期的なツールです。(ここらあたりは真面目に話し出すときりがない)
深く信頼してもらうために
今回のライブ配信は面白い手段だな、と思いました。
私のみならず一緒に出演してくれた人も信頼が深くなりますね。
オンライン飲み会のライブ配信は
結構難しい
単独のライブ配信はそれほど難しくありません。自分一人苦労して調べれば解決します。
ですが、
「オンライン」という場で「複数人が同時にオンラインにつなぎ」「飲んでいる人間に視聴者のことを考えてもらいつつ話してもらう」のは結構難しいです。
・配信環境を整えている私の通信環境が乱れると全部終わり
・相手さんの通信環境が悪くても終わり
・週末なりでネット回線が混んでも終わり
・飲みはじめて酔っ払うと終わり
うん、見れば見るほど綱渡りですね、
この動画配信は。(;・∀・)
話は面白くしようと事前に「こういう話を聞きますね」「私は知っているけど、視聴者さんが聞きたがりそうなこういうネタを振りますね」「こういう写真を使って話を投げます」などの打ち合わせはしています。これをやらないとほんとにグダグダに。
ま、そこまでやったけど、今回私の通信環境のせいでグダグダになったんですけどね!_| ̄|○
でも、失敗は経験値です。
悔しさは未来の原動力です。
一緒に出演してくれた二人からは「悔しいからまたリベンジやろう!」との声をいただけましたので、またやると思います。興味ある方はまた御覧くださいな。
質問と回答
・バーチャルYoutuberにはならないの?
すいませんね、むさっ苦しい顔で。(;^ω^)
私のようにイベントをやったり、blogを実名で書いてきた人間は顔出しして顔を売るほうがメリットは、でかいです。
これ読んだ中で「私は実名を出したくないんだ」という方は、最初に名刺を作る時点でビジネスネームなり芸名なりを作っておいたほうが良いです。
当初から本名でやってきた私のような人間は、顔を出さないメリットはもうほぼないですね。
・lineライブやfacebookの配信じゃ駄目なの?
それらですと、放送後の動画を保存しておくのがめんどくさい・遠隔地の人と対談しているのをオンラインでライブ配信できない、などのデメリットがあります。
You Tubeライブ配信だと配信した動画をそのままYou Tubeにアップすることも可能です。また配信ソフトOBSは「配信しつつ録画」機能もあります。
環境整えたり、設定がめんどくさいですが、後々にコンテンツを再利用しやすいです。
今だからこそ、
新しいことをやりやすい
日本、という国は黒船が来ないと動かない保守的な国だと思っています。今回新型コロナウィルス、という黒船が来ました。目に見えやすいトラブルがあると解決に動くんだ、この国民は。。。
メーカーさんからは
「5月いっぱいの仕事だけで今後が不安だよぅ」という声ももらっています。
「逆にチャンスやで。
今なら社長とかが焦っているときだから、『こういう新しいことしましょう!』という提案は通りやすいかな。」と答えました。
2か月後は通りづらくなっているから焦ったほうが良いとは思うけどね。
March 25, 2020
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/コロナウィルスと革製品の話
カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」
毎度です!「時代は世紀末的だなぁ」ムラキです。
最近はどこに行ってもコロナコロナ、です。まさかこんな時代が来るとは数ヶ月前には想像もできませんでしたね。
で、facebookを見ていると、「スマホを消毒するついでに革製品も消毒スプレーしたら色が剥げた!」という話がありました。今回のblogでは「革製品にも消毒したほうがいいのか?」「コロナウィルスに対してマスクがないと駄目なのか」「予防には何をすれば良いのか」というような話を書いていきます。
※今回のblogで使う資料はネットにあげられた厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症について」・WHO、公的な医療機関の発表から引用します。Twitter・インスタ・個人blogにあがっている情報、メディア情報は確実性に欠けるためここでは紹介しません。
目次 [hide]
革のスマホカバーに消毒
革製品にアルコールをつけることは正しいのか?
革製品についたコロナウィルスが怖いので消毒したほうがいいのか?
コロナウィルスは飛沫感染と接触感染の2ルートで感染する
ビニール袋をめくるために指先につばを付けたり、鼻をほじっても、キスをしても感染リスクはある
ウィルスはどこに付着して、どれくらい生存するのか?
革だけ消毒してもあまり意味はない
マスクはコロナウィルスに対しての万能防御にはならない
感染予防は何をするべきか?
新型コロナウイルス感染症の予防
外出する際は密を避けて外出しましょう
コロナの話ばかりじゃなくて、西の革業界の話もしてください

4年愛用してるスマホカバー!ワキシングレザーというオリジナルレザーを使ってるんですが、手の油分で艶がどんどん増してきたんですが...
コロナウイルスのニュースを見て「スマホ毎日触ってるし、不衛生かも...」→アルコールで表面を拭く→色が若干抜けて艶が曇る→焦る→手の平で思いっ切り擦りまくって油分を補う?
なんとかここまで復活しましたいや〜マジ焦りましたわ〜
レザー大好きな方々や、詳しい方々は既にご存知かと思いますが、アルコールで拭いちゃダメですからね!絶対マネしないで下さいね〜このスマホカバー、前よりもさらに良い雰囲気になったかも
という書き込みをfacebookで見かけました。投稿者に許可をもらい、写真と文章をお借りしました。
で、結論から言うと「手洗い消毒アルコールで革製品を消毒したら駄目」です。
革製品にアルコールをつけることは正しいのか?
基本的にオススメできません。
消毒用のアルコールの濃度は様々ですが、60%~90%ほどはあります。
これだけの濃度があると染料仕上げの革は染料を落としてしまいます。顔料仕上げの革でも表面保護として載っているクリア塗装を落としてしまいます。そうなるとその部分だけ艶がなくなる・くすむ、などの現象が生じます。
表面の消毒なりをしたいならば、革用のクリーナーなりをオススメします。
抗菌クリーナー | コロンブス オンラインショップレザークリスタル クリーナー | コロンブス オンラインショップ
上記以外にも「レザークリーナー」などの名前がついているものがオススメです。でも、オススメしておいてなんですが、革製品に付着しているかもしれないコロナウィルスを恐れてもあまり意味がないかもしれません。
革製品についたコロナウィルスが怖いので消毒したほうがいいのか?
回答は「それだけでは意味がない」となります。これは消毒が意味ない、というわけではなく、「革製品だけ消毒しても意味がない」という意味での回答となります。
順をおって解説してみましょう。
コロナウィルスは飛沫感染と接触感染の2ルートで感染する
飛沫感染とは?
感染した人の咳・くしゃみ・つば・鼻水など飛沫(とびちったしぶき)の中に含まれているウイルスを口や鼻から吸い込むことにより感染することです.
接触感染とは?
ウイルスが付着した手指で鼻や口や目に触れることで、粘膜などを通じてウイルスが体内に入り感染することです。
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手でドアノブ、スイッチ、手すりなど周りの物や場所に触れるとウイルスが付きます.他の人がその物や場所を触るとウイルスが手に付着し、その手で口、鼻、目を触ることで粘膜から感染します。
上記にありますように
「くしゃみ、咳、つば、などでウィルスが放出され、それが口鼻などから吸い込んで感染する」
「感染者の手に付着したウィルスが、日常生活で他のものに付着し、非感染者がそれを触り、口鼻を触ると粘膜から感染」
の2つが主要な感染経路です。
ビニール袋をめくるために指先につばを付けたり、鼻をほじっても、キスをしても感染リスクはある
ドアノブ、スイッチ、手すりに触ることでウィルスが付着した場合、その後にビニール袋をめくるために指先につばを付けたり、鼻をほじっても感染する可能性があります。
また、目がかゆいから手でこする・鼻の頭がかゆいからゴシゴシと掻く際に、目鼻の粘膜に触れてしまい、そこから感染することもありえるわけです。
ウィルスはどこに付着して、どれくらい生存するのか?
これに関して厚生労働省は明確な数字をまだ出していません。2003年のSARSのときは下記にように報告されています。
実際、SARSコロナウイルスは患者の気道分泌物以外に、糞便、尿からも長期間排出されることが確認されている。既知のコロナウイルスの場合、外界での生存時間はおおむね3時間とされているが、WHOの発表によれば、SARSコロナウイルスは乾燥したプラスチックの表面で72時間生存できる。また糞便や尿中でも48時間生存が可能であり、さらに下痢患者の便はpHが高いため生存期間は4日間とかなり長い。
SARSとコロナの生存時間が同じ、とは言えませんが、プラスチック表面でも72時間は生存する可能性があるわけです。米疾病対策センター(CDC)は空気中3時間、プラスチックやステンレス表面で2~3日間生存、という報告を出しています。
革だけ消毒してもあまり意味はない
ウィルスの付着はどこにでも起こりえます。
手すりドアノブは言わずもがなですが、お使いのスマホ・手帳・鞄・靴・服、などあらゆるものに付着し、数時間~72時間生存する可能性があるわけです。
だからこそ、「革製品だけ消毒してもあまり意味はない」わけです。消毒するならばありとあらゆる品を消毒し、手で目鼻口などの粘膜部分に触らないことです。
実際問題、今現在飲食店などは食器以外にも机椅子なども消毒しており、その手間隙が莫大になってきています。
また、「マスクを装備しているから大丈夫!」なんてことは全くありません。
マスクはコロナウィルスに対しての万能防御にはならない
マスクは万能防御道具ではありません。
コロナウィルスに対してマスクをつけるメリットは2つ
(1)咳・くしゃみなどの症状のある人が使用する場合
咳・くしゃみなどの症状のある人は、周囲の人に感染を拡大する可能性があるため、可能な限り外出すべきではない。また、やむを得ず外出する際には、咳・くしゃみによる飛沫の飛散を防ぐために不織布製マスクを積極的に着用することが推奨される。これは咳エチケットの一部である。(2)健康な人が不織布製マスクを使用する場合
マスクを着用することにより、机、ドアノブ、スイッチなどに付着したウイルスが手を介して口や鼻に直接触れることを防ぐことから、ある程度は接触感染を減らすことが期待される。
また、環境中のウイルスを含んだ飛沫は不織布製マスクのフィルターにある程度は捕捉される。しかしながら、感染していない健康な人が、不織布製マスクを着用することで飛沫を完全に吸い込まないようにすることはできない。
よって、咳や発熱等の症状のある人に近寄らない(2メートル以内に近づかない)、流行時には人混みの多い場所に行かない、手指を清潔に保つ、といった感染予防策を優先して実施することが推奨される。
やむを得ず、新型インフルエンザ流行時に外出をして人混みに入る可能性がある場合には、ある程度の飛沫等は捕捉されるため、不織布製マスクを着用することは一つの防御策と考えられる。
ただし、人混みに入る時間は極力短時間にする。
新型インフルエンザ流行時の日常生活におけるマスク使用の考え方
・今の時期は花粉症やアレルギー反応で咳が出ることがあります。私自身が2月になると咳がでるアレルギー持ちです。最近は公共の場で咳をするとギョッとした顔で見られたりします。(´・ω・`)
私のようなアレルギー持ちはマスクをつけることで「人に移しませんよ」という咳エチケットとなります。
「咳エチケット」は、これらの感染症を他人に感染させないために、個人が咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえることです。
咳エチケットより
マスクがない状態で咳が出そうな際は、手で覆えばok!ではなく、下記のようにガッチリとガードすることを咳エチケットでは推奨されています。
咳エチケットより
・非感染者がマスクをするメリットは?
マスクをしたからといって感染予防100%にはなりません。マスクをすることで目鼻口などの粘膜に触れづらくなることが予防としてのメリットになります。マスクをしたからといって安全!と思うことなく、こまめな感染予防を行うべきなわけです。
感染予防は何をするべきか?
基本は手を洗う・咳エチケットを守る・"密"を避ける、です。
新型コロナウイルス感染症の予防
風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
風邪症状があれば、外出を控えていただき、やむを得ず外出される場合にはマスクを着用していただくようお願いします。まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。
咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。
外出する際は密を避けて外出しましょう
集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」です。
換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。
コロナの話ばかりじゃなくて、西の革業界の話もしてください
「ムラキさん、新型コロナウィルスの話ばかりじゃなく、西の革業界の話もしてください」
今回、新型コロナウィルスのおかげで4/3-4予定だった「本日は革日和♪in 大阪」も延期としました。
で、それじゃなんですので、西の革屋さんをふらふらと巡り。
「ちゃーす!
かくかくしかじかで西の革屋さんの新作革、できれば国産のを紹介したいんですけどなにかあります?」と押しかけたところ皆さん快く紹介してくれました。
革の写真はこちらです。
「ふんわり」「もっちり」という質感はレザーでも人気のようです。国内のつくり手たちが仕上げた革は、色合い・風合いに優れています。
くわしい情報などはリンク先をご覧ください。
February 26, 2020
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/靴業界における弟子システムとはどのようなものだったか
カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」
毎度です! 「最近TELしたら東京の方でも『毎度です』と帰ってくるようになってきた」ムラキです。大阪商人めんどくさいなぁ、とか思われているのかなぁ( ゚Д゚)y─┛~~
前回のblogでは「職人になりたい!」という人向けに職人というものの定義や職人になるために何をすればいいかを軽く紹介してみました。
「人に話したくなる革の話」/キッズレザープログラムと「職人になりたい!」という人向けの話
で、それを見た人から「弟子入り、というのは可能なの?」という相談がありましたので、いつものごとく様々に話を飛びながらこの国の革産業における弟子というものについて解説していきたいと思いますわ。
目次
職人の定義をもう一度
至高の靴職人 関信義-手業とその継承に人生を捧げた男がいた
大塚製靴百年史
職人の定義をもう一度
革業界においては職人、という定義はされていません。「この資格を持っていたら職人」「これができたら職人」ということはないわけです。基本的には「自称職人」、の世界です。
ですので、メーカーで10年働いて職人、と名乗る人もいるし、どこかの学校なり教室卒業して職人、と名乗る人もいます。メーカーからもらった仕事をひたすら行う請負職人、という人もいますし、百貨店の「日本の職人展」で接客しながら販売する職人さんもいるわけです。
職人、という言葉に対して個々人の使い方が異なるので「自分が意味する使い方と違う!だからあいつは職人じゃない!」というのはお門違いですよ、というのがこの項目の趣旨です。
弟子入り、という制度はどのようなものだったか?
上記は今回のためにひっくり返した私の趣味の「革に関する蔵書」の極々一部です。
大前提として、靴業界は資料が残っています。日本の製革の歴史は明治時代からスタートであり、その際も軍需品としての靴がスタートでした。奈良時代なり、戦国時代なり江戸時代などにも革産業はあるのですが、革が大量に生産されたのは明治時代からです。
で、軍需と結びついていると記録がきっちり残ります。おかげで今現在も多数の本を読むことが出来ます。個人的に革に関する書籍を集めていますが、鞄財布などはほんとに少ないです(;・∀・) たまにあってもそれは「鞄メーカー」としての記録なりであり、「鞄職人」の記録はほとんどありません。「財布職人」に関しては現状私も見つけきれていません。
例えば鞄のエース創業者 新川柳作氏は自伝を残してくれており、読み応えがあり面白いです。ただ、それは鞄メーカーを興した人物の自伝であり、「鞄を作った職人さん」の記述は非常に少ないです。下記サイトで自伝の一部が読むことが可能です。
新川柳作記念館 Ryusaku Shinkawa Museum|エース株式会社
それに対して靴職人に関しては職人さん自身or他者なりが書いた本がそこそこの数が残っています。で、それを見てみましょう。
本で見る日本の靴業界における徒弟制度
至高の靴職人 関信義-手業とその継承に人生を捧げた男がいた
あらすじ
日本最高峰の靴職人の半生を追う
日本最高峰の靴職人、関信義さんが70歳を超え、いよいよ引退することを決めました。関さんの名は、ファッション業界関連の者なら知らぬ人はいないほど。その半生を振り返り、いかにして最高峰の称号を得るにいたったのか、関さんが生きた靴業界はどのようなものだったのか。大量生産の時代の終焉を迎えようとしている今、自らの命を削りながら、後継者を育てる職人の生き様を追いかけます。
私自身は関信義氏とは面識がなく、「至高」なのかどうかはここでは触れません。知りませんので。決して「わぁ、皮革産業連合会のBLOGに載っているから一番正しいんだ」と早とちりしないでくださいね。後で私がJLIA上層部から怒られますので(;・∀・)
竹川圭氏が聞き取った上で書き連ねたもののため、かなり読みやすい本です。また、戦後の靴職人の飲む打つ買うなり喧嘩っぱやさなども記録されており面白く読めます。これを読むと高齢の靴職人さんが「えっ!大学出てなんで靴職人になりたいの?」という気持ちもわかります。
で、この本では17歳の関信義氏の修行時代(1957年)が書かれています。三和、というのは靴メーカーさんの名前です。
・小僧の朝は6時。食堂ではおかみさんと姪っ子が育ち盛りのための朝食を用意して待ち構えている。いたるところで「お代わりっ」の声が飛び、女たちは「はいはい」といってどんぶりに湯気の立った飯を盛る。さながら戦場のような空間に四羽ガラスは平然と混ざり、負けじと飯をかっ込んだ。
三和はタダメシを食わせるだけでなく、月500円の小遣いもくれた。知り合いの大工の小僧に比べれば少なかったが。それでも2日に1度は銭湯に通え、月に1度は映画もみられたので文句はなかった。誰よりも早く仕事を覚えていった関がかわいかったのか、おかみさんはことあるごとにこっそりと駄賃をくれたのでなおさらだった。製靴業は猫の手も借りたいぐらい、仕事があふれていた。戦後主役の座に躍り出たサラリーマンにとって。靴はまずは手に入れなければならないひとつだった。
(至高の靴職人 関信義 p61)
そのころの日本人は大人も子どもも荒っぽかったが、職人の世界は輪をかけてひどかった。小僧は職人の仕事をみて覚える。徒弟制度のこのルールも、一筋縄ではいかない。作業台に近づこうものなら「じゃまくせえ」と一蹴され、遠巻きに眺めていても「みてんじゃねえ」とすごまれる。関はずいぷんと理不尽な育て方だと思った。
(至高の靴職人 関信義 p65)
小僧の日々に慣れてくると、合間合間にくず革を使って針を刺す練習が許されるようになる。辻が手つきをみて、あるとき、仕掛かりの靴の数針を縫わせてくれる。たいがいは口汚くののしり、この糸はよく締まっているなとごくたまに褒める。うれしくなって前のめりになる自分を冷静にみているもうひとりの自分がいて、うまいことやるもんだなと心のなかでは思っていた。
(至高の靴職人 関信義 68p)
小僧2年といわれる修行期間を、関は1年あまりで駆け抜けた。2年程度の下積みというのは素人に毛が数本生えた段階であり、予習があればもっと時間をかけたいのが経営者の本音である。しかし次から次へとやってくる仕事をこなすには職人はいくらいても足らず、また、いつまでもただ養っているわけにもいかない。半ば強引に一本立ちさせるための制度が"小僧2年"であり、関への処遇は例がなかった。
(至高の靴職人 関信義 71p)
小僧を卒業すると、奉公返しと呼ぶ2年が幕を開ける。
奉公返しとは世話になった礼に、相場の半値で靴をつくる期間を指す。
(至高の靴職人 関信義 97p)
関信義氏からの聞き取りによりこの当時の弟子システムが色々とわかります。
・靴職人、というのはこの場合受け取りの量産職人
「1年で出す」
3ヵ月経って、作業台と椅子をつくってやった。弟子入りをみとめた証だった。
仕掛かりの靴を渡して1から叩き込んでいった。不合格ならバラしてやりなおさせた。
1回は許しても、2回目の失敗には容赦なく雷を落とした。玲子は歯を食いしばってついてきた。毎日弁当をつくってきて、朝は早くから日が暮れるまで作業に没頭した。
弁当を食べ終わると、地べたにぺたりと座り込んで、じっとしているのが印象的だった。身体の隅々へ効率よく栄養をいきわたらせるぺく、無意識にやっていたのだろう。午後からの作業に具える姿は充電中のロボ″卜を思わせた。
そのうち小遣いをやるようになった。
玲子はもち前の負けん気で一つひとつ確実に手になじませていった。関の読みを上回るペースで上達をみせ。約束の1年が経つころにはひと通りのことがこなせるようになった。
いれば学ぶことはいくらでもある。ついつい手もとにおいておきたい気持ちが勝って、ずるずると卒業を先延ばしにしていた。
(中略)
「あ、関だが。うちで面倒みた若いのがいるんだが、そっちで使ってくれないかね」
ひとり立ちさせることを決めた関は、かつて籍をおいた三田製靴に声をかけた。
(至高の靴職人 関信義 18.19p)
こちらは冒頭第1章「はじめての弟子」からの引用です。関信義氏が近年弟子を取った際の教え方が書かれています。
・お金は渡さずある程度できるようになったらお小遣いを渡していた
これだけ見るとえげつないように見えるが、師匠は弟子が独立する際には「こいつは俺が育てた弟子だ」「だから取引先さん、よろしく見たってな」と声がけする義務的なものもあったわけで。
技術だけではなく、師匠がもつ信頼も一緒に渡していたわけです。
大塚製靴百年史
大塚製靴さんが昭和50年頃に出した百年史。この中で「職人はここまで出来たら2級」などしっかりと規定されていました。今回の弟子入り、とは違う話ですが、この当時にこれだけしっかりとした基準を定めているのはすごいですな。
日本のモノづくりをする人は「弟子」という言葉が好きすぎる
過去にも書きましたが、日本人は「職人」や「モノづくり」という言葉がすごく好きです。また、それに付随する弟子、という言葉も大好きです。
それはそれで構わないと思っています。ただ、「弟子、というのは金銭をたいして払わずに使っていい人材」というわけではありません。過去の時代でも衣食住保障+お小遣いは支払っていました。
関信義氏が近年弟子を育てた際は「通いで来てもらう」「当初は金を支払わず使う。ある程度育ったらお小遣いを支払う」「見込みなかったら早期に『お前は向かない』と引導を渡す」などをしていました。
弟子システムを師匠が取る最大のメリットは薄給で使えることではなく、育った後に下請け仕事先として依頼する協力相手を作る、ということだと私は思っています。そのためには「猫の手も借りたいほど忙しい仕事」が存在しないと弟子も取れません。
また、師匠は弟子に対して「この仕事を習得すると将来これだけ食べれる」という未来図を提示してあげるべきだと思います。まぁ、だからこそ今の時代「食っていけるわけでもないし、君をそばに置いておくほど仕事ないから弟子入りは認められない」と言われるわけですが。
実際に当時を知っている人に話を聞いてみた
大阪で靴の型紙制作・型紙講座を開いている古瀬勝一氏。先日「東京レザーフェア」(2019年12月)の際に靴の制作実演をしていただきました。
村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/豊岡鞄のセミナーを聞いたり、型紙セミナーを運営して思った 知ってもらう大切さの話
で、この古瀬氏、実家が靴メーカーでした。お父さんが師匠として弟子も多数雇っておられました。ですので当時を聞いてみました。
(★以下、「」内が古瀬氏の話です)
・
「当時、、、1970年代手前くらいですかねぇ。僕が小学校の頃でした。家は靴メーカーでしたね。メーカーと言っても自宅兼工房みたいなものでしたよ。父は面倒見が良い人でした。衣食住完備でお小遣いもあげていましたね。お小遣いは多くはありませんが、映画見に行くなりパン買うなりしていましたね。
当時お小遣い以外にも母が積立をしていました。独立する際に通帳と印鑑を渡して『無駄遣いするんじゃないよ』と言いながら渡して送り出していましたねぇ」
自宅兼工房、ということは弟子と一緒に暮らしていたってことですか?
「もちろんです。父は『弟子が優先』という考え方でした。
例えばすき焼きを食べるときは父と弟子が優先でした。僕と兄は弟子たちが食べたあとの残りを食べさせられていましたね。だから幼い僕にとってはすき焼きってのは鍋の底に残ったドロドロのものでしたねぇ。(^_^;)」
えっ!親方の息子だからでかい顔できた、とかなかったの?
「ありませんありませんよ!
例えばTVなんかは父が最優先でプロレスや野球見ていました。その後に弟子が見たいものを見る、みたいな。子どもたちが見たい8時だよ!全員集合、なんかはなかなか見れませんでしたね。
銭湯も弟子と父が一緒に行き、父がお金出していましたね。
父はアメとムチをきっちり使い分けられる人でした。そりゃ仕事では厳しかったですが、生活ではアメを与えていましたね。例えば、うちは扇風機やクーラー、車が家に導入されるのは遅かったんですよ」
??なんで?
「父が『独立した弟子がきちんと扇風機orクーラーor車が買えるようになったらうちも導入する!』という考え方でした。だから自転車の後ろに靴を140足入れた箱をくくりつけて納品したりしていましたね。原付き運転できる弟子が入ったときにスーパーカブを導入しました。 他にも結婚、出産などがあった際には祝い金も出していましたね。
ムラキさんが言わはる奉公返し、とかはなかったです。うちのメーカーが下請けに出す金額と同じだけ、独立した弟子に払っていました。で、お金をためて扇風機or車なり買ってがんばれよ!と言っていましたねぇ。まぁ、こういうシステムは今の時代運用は難しいですよね」
ドイツはマイスターでギルド、というシステムが有る
ドイツ靴文化論講演会 7/7 in大阪 上田安子服飾専門学校 | phoenix blog
2016年に行われたセミナーで【ドイツ靴職人の修行と労働環境の推移】というものがありました。当時から弟子システムなどについて調べていた私からしたら非常に面白い内容でした。
日本では「ドイツにはマイスターと職人が尊敬されている」「ギルド、という職人組合がある」、というくらいの認識かと思います。ですが、私個人が思ったよりも遥かにマイスターという言葉は重く、また義務もありました。
・マイスターは国家資格
・ドイツ手工業組合がある
>連邦共和国法律下で手工業領域全般の資格試験(GESELLE^MEISTER)の運営菅理
>MEISTERの労働環境や地域でのパワーバランスを管理(独立店舗を持つうえでの立地的調査・調整)
>検査機関としてマイスター試験など各種試験が公正適切に行われたか、政府に定期的にレポート
>GESELLE・MEISTERのためのスキルアップセミナーの開催
>労働法などの法的アドバイス
>MEISTERやエンドユーザー、弟子間の問題仲裁などを行う
・インヌング=職人協会が中世から存在する。
>職業別に特化した組織
>職業規定・倫理規定・同業者との地域連携、弟子の育成環境が適正かチェック・管理
>弟子に対してのケア。訓練場所のレベルや公正な修行、技術指導が行われているか定期的にチェック
>弟子や職業訓練場所との問題解決・仲裁
>協会員とエンドユーザー間で起きた問題の仲裁
>セクハラ・パワハラがあった場合の指導・仲裁
ドイツは職人の国、といわれますが、日本よりも遥かに職人に対する教育体制や法的・組合の義務が多く存在するのが印象的でした。だからこそ、国民が職人に敬意とお金を払うんだろうな、とも思います。
ここらの話に興味ある方は下記などが参考になるかと思います。
ドイツのマイスター制度 - マイスター制度を理解するためのキーワード - ドイツ生活情報満載!ドイツニュースダイジェスト
pdf:英国における皮革業の社会史:比較文化史の視点から 1
先日大阪でバッグメーカーさんのセミナーをしました
大阪府皮革業界総合研修、という毎年大阪府が行ってくれる研修事業があります。大阪府さん、毎年毎年ありがとうございます!(*´ω`*) 革の解説に関してはプロ中のプロの人が来てくれたり、越境ECの話など今年も盛りだくさんでした。(新型コロナウイルスの影響で後半中止になっちゃいましたが。。。)
で、今回2つのセミナーの段取りを組んでほしい、と言われ協力。そのうちの一つが西川商店さんを呼んで「気持ちよく働ける会社作りで、人が人を呼ぶ。」という内容で話していただきました。
大阪府皮革業界総合研修 第1回が面白かった&今後の予定セミナーが濃ゆい | phoenix blog
このセミナーでは私は黒子というか太鼓持ちというか、司会を行いました。事前に聞き取り調査をし、レジュメを作り、「当日このように質問します、でも1割ほどアドリブで聞きます」というような脚本も書きました。芸人ならばいざしらず、普通の人は「はい、セミナーしますので喋ってくださいね。あとお願いね!」と言っても出来ません。また、本音も喋れません。ですので「で、うちの主力の生産の子が独立したいと言い出しまして」「えっ!困りますやん!」「そうなんですよ!」などのツッコミ・合いの手を入れるのが私の役割でした。関西人の7割はツッコミとボケができるんですよ
「気持ちよく働ける会社作りで、人が人を呼ぶ。」というタイトルだけあって、どのように働くひとに来てもらっているか、という話が中心。福利厚生もしっかりとした状態で人を募集し、弟子・師匠というシステムとは異なります。ですが、しっかりとした教育システムの下で人を育てるのがわかるセミナーでした。
ツッコミ入れつつ「なるほど、今の時代はここまで整えないとモノづくりの会社で働きたいんだ!という人を惹きつけられないんだなぁ」と冷や汗をかきました。
さて、最初の質問「弟子入り、というのは可能なの?」という回答
弟子に入りたい、という人に対しての回答です。
・技術を学びたいだけならば教室なり学校がオススメ。
ついでに師匠or人を雇う、という革関係の会社の方向けの提言
・「見て覚えろ」「俺の若い頃は」は今の時代通らないです
・下記の本、いいですよ
「新たな"プロ"の育て方」amazon
左官屋が若い人をどう育てたか、という内容。根性論などではなく、今の若い人向けにはこう教えないと技術は教えきれない、という内容。
作者blog>書籍を執筆した思い「新たなプロの育て方」 - 原田左官のブログ
ムラキの今後予定。手前味噌ですが、、
・2月28日(金) 16:00~18:00 とすぐですが、大阪のA´ワーク創造館(googlemap)で下記セミナーを行います。
特別セミナー「人に話したくなる革の話〜新世代のモノづくりは何をどのように活用しているか」のご案内 | シューカレッジおおさか
メーカーさん向けの話となりますが「モノづくりで食べていきたい」などの人にも得るものはあるかと思います。オチを最初に言うならば「技術や新素材があるからって食っていけるわけじゃない」というものとなります。「じゃぁ何が必要なのか」というのがセミナーの流れとなります。
・4月3,4日(金,土)は革日和in大阪となります。大阪の革屋さんの感謝市や展示会を予定しています。また革日和告知ページなどで随時、最新情報を公開予定です。
 プロフィール
プロフィール

鈴木清之(SUZUKI, Kiyoyuki)
オンラインライター
東京・下町エリアに生まれ、靴・バッグのファクトリーに囲まれて育つ。文化服装学院ファッション情報科卒業。文化出版局で編集スタッフとして活動後、PR業務開始。日本国内のファクトリーブランドを中心にコミュニケーションを担当。現在、雑誌『装苑』のファッションポータルサイトにおいて、ファッション・インテリア・雑貨などライフスタイル全般をテーマとしたブログを毎日更新中。このほか、発起人となり立ち上げた「デコクロ(デコレーション ユニクロ)部」は、SNSのコミュニティが1,000名を突破。また、書籍『東京おつかいもの手帖』、『フィガロジャポン』“おもたせ”企画への参加など、“おつかいもの愛好家”・”パーソナルギフトプランナー”としても活動中。
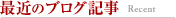 最近のブログ記事
最近のブログ記事
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年7月(1)
- 【村木るいさん連載】キッズレザープログラムに届いた小学生からの難しい質問とジャパンレザーアワードの話
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(3)
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(2)
- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(1)
 カテゴリー
カテゴリー
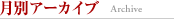 月間アーカイブ
月間アーカイブ
- 2024年7月 ( 1 )
- 2024年6月 ( 4 )
- 2024年5月 ( 5 )
- 2024年4月 ( 4 )
- 2024年3月 ( 3 )
- 2024年2月 ( 4 )
- 2024年1月 ( 4 )
- 2023年12月 ( 4 )
- 2023年11月 ( 5 )
- 2023年10月 ( 4 )
- 2023年9月 ( 4 )
- 2023年8月 ( 4 )
- 2023年7月 ( 4 )
- 2023年6月 ( 4 )
- 2023年5月 ( 4 )
- 2023年4月 ( 4 )
- 2023年3月 ( 5 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年12月 ( 4 )
- 2022年11月 ( 4 )
- 2022年10月 ( 4 )
- 2022年9月 ( 4 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 4 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2022年5月 ( 3 )
- 2022年4月 ( 4 )
- 2022年3月 ( 5 )
- 2022年2月 ( 4 )
- 2022年1月 ( 4 )
- 2021年12月 ( 4 )
- 2021年11月 ( 3 )
- 2021年10月 ( 4 )
- 2021年9月 ( 5 )
- 2021年8月 ( 3 )
- 2021年7月 ( 4 )
- 2021年6月 ( 5 )
- 2021年5月 ( 3 )
- 2021年4月 ( 4 )
- 2021年3月 ( 5 )
- 2021年2月 ( 4 )
- 2021年1月 ( 4 )
- 2020年12月 ( 4 )
- 2020年11月 ( 4 )
- 2020年10月 ( 4 )
- 2020年9月 ( 5 )
- 2020年8月 ( 3 )
- 2020年7月 ( 5 )
- 2020年6月 ( 4 )
- 2020年5月 ( 3 )
- 2020年4月 ( 4 )
- 2020年3月 ( 4 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 4 )
- 2019年12月 ( 4 )
- 2019年11月 ( 4 )
- 2019年10月 ( 5 )
- 2019年9月 ( 4 )
- 2019年8月 ( 3 )
- 2019年7月 ( 5 )
- 2019年6月 ( 4 )
- 2019年5月 ( 4 )
- 2019年4月 ( 4 )
- 2019年3月 ( 4 )
- 2019年2月 ( 4 )
- 2019年1月 ( 4 )
- 2018年12月 ( 4 )
- 2018年11月 ( 4 )
- 2018年10月 ( 5 )
- 2018年9月 ( 4 )
- 2018年8月 ( 4 )
- 2018年7月 ( 4 )
- 2018年6月 ( 4 )
- 2018年5月 ( 5 )
- 2018年4月 ( 4 )
- 2018年3月 ( 4 )
- 2018年2月 ( 4 )
- 2018年1月 ( 4 )
- 2017年12月 ( 4 )
- 2017年11月 ( 5 )
- 2017年10月 ( 4 )
- 2017年9月 ( 4 )
- 2017年8月 ( 4 )
- 2017年7月 ( 4 )
- 2017年6月 ( 4 )
- 2017年5月 ( 4 )
- 2017年4月 ( 4 )
- 2017年3月 ( 5 )
- 2017年2月 ( 4 )
- 2017年1月 ( 3 )
- 2016年12月 ( 4 )
- 2016年11月 ( 5 )
- 2016年10月 ( 4 )
- 2016年9月 ( 4 )
- 2016年8月 ( 4 )
- 2016年7月 ( 4 )
- 2016年6月 ( 5 )
- 2016年5月 ( 3 )
- 2016年4月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 5 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 4 )
- 2015年12月 ( 4 )
- 2015年11月 ( 4 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 5 )
- 2015年8月 ( 3 )
- 2015年7月 ( 5 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 4 )
- 2015年4月 ( 5 )
- 2015年3月 ( 4 )
- 2015年2月 ( 4 )
- 2015年1月 ( 4 )
- 2014年12月 ( 4 )
- 2014年11月 ( 4 )
- 2014年10月 ( 5 )
- 2014年9月 ( 4 )
- 2014年8月 ( 3 )
- 2014年7月 ( 5 )
- 2014年6月 ( 4 )
- 2014年5月 ( 4 )
- 2014年4月 ( 5 )
- 2014年3月 ( 4 )
- 2014年2月 ( 4 )
- 2014年1月 ( 4 )
- 2013年12月 ( 4 )
- 2013年11月 ( 4 )
- 2013年10月 ( 5 )
- 2013年9月 ( 4 )
- 2013年8月 ( 3 )
- 2013年7月 ( 5 )
- 2013年6月 ( 4 )
- 2013年5月 ( 5 )
- 2013年4月 ( 4 )
- 2013年3月 ( 4 )
- 2013年2月 ( 4 )
- 2013年1月 ( 4 )
- 2012年12月 ( 4 )
- 2012年11月 ( 4 )
- 2012年10月 ( 5 )
- 2012年9月 ( 4 )
- 2012年8月 ( 4 )
- 2012年7月 ( 4 )
- 2012年6月 ( 4 )
- 2012年5月 ( 5 )
- 2012年4月 ( 4 )
- 2012年3月 ( 4 )
- 2012年2月 ( 5 )
- 2012年1月 ( 3 )
- 2011年12月 ( 3 )
- 2011年11月 ( 5 )
- 2011年10月 ( 4 )
- 2011年9月 ( 4 )
- 2011年8月 ( 5 )
- 2011年7月 ( 4 )
- 2011年6月 ( 5 )
- 2011年5月 ( 4 )
- 2011年4月 ( 4 )
- 2011年3月 ( 5 )
- 2011年2月 ( 4 )
- 2011年1月 ( 4 )
- 2010年12月 ( 4 )
- 2010年11月 ( 5 )
- 2010年10月 ( 4 )
- 2010年9月 ( 4 )
- 2010年8月 ( 5 )
- 2010年7月 ( 4 )
- 2010年6月 ( 4 )
- 2010年5月 ( 5 )
- 2010年4月 ( 4 )
- 2010年3月 ( 5 )