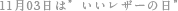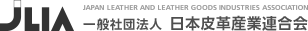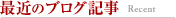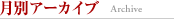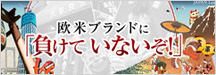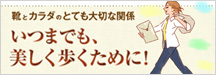10/31(木)~11/4(月) 姫路城皮革フェスティバル
姫路城皮革フェスティバルは革素材をタンナーさんが直接販売したり、革製品の販売なども行われます。どちらかというと素材のほうが多いかな。それよりも多いのは同会場の併設イベントである「陶器市」のほうが全国から出展者が来られています。さらに「姫路菓子まつり」もあり、お子さん向けの企画なども充実しています。
秋の日の1日を家族みんなで楽しめるイベントとなっています( ´∀`)bグッ!
会期
令和元年10月31日(木曜日)から令和元年11月4日(月曜日・振替休日)まで
各日 午前10時00分から午後5時00分まで
開催場所
アクセス
姫路駅を降りてお城に向かってテクテクと歩ける距離です。歩いて10分弱くらいです。
周辺に駐車場もちらほらとありますが、イベント期間中は渋滞しがちです。
天気がいいならばお城を眺めつつ、ちょっと離れた駐車場に停めてテクテク歩くのもおすすめです。
2018年の様子
FB: 姫路城皮革フェスティバル2019
こちらは昨年のblogで紹介したものです。
昨年の様子はこんな感じです。製品販売もありますが、素材販売も同じくらいあります。
今年の姫路城皮革フェスティバルフライヤー
同会場で陶器市も行われています。陶器好きならば是非
同会場で同じ期間中陶器市も開催されます。かなり規模が大きく、料理をする人や陶芸が好きな人は1日遊べるほど展示販売されています。
姫路全国陶器市2019 全国の焼き物たちが大集合!お買い得価格で【兵庫県】 | 陶器市情報ブログ
同会場で姫路菓子祭りも開催されます。
こちらも同会場、同期間で行われます。
ちなみに姫路は和菓子のお店が多い土地柄です。 江戸時代の後期、藩主酒井家の歴代の当主が教養人であり、茶の湯を好んだことから姫路城下の文化は大いに発展することになりました。しかし、天保年間の藩主酒井忠以の頃、財政は窮乏、家老の河合寸翁は財政再建を志し、藩政改革を行うと共に、諸国の物産を城下に集積して商業、物流を盛んにしました。この寸翁が藩主同様茶人であったことから、産業振興の一環として和菓子づくりを奨励、職人を江戸や京都、長崎まで派遣し、製造技術を習得させました。
そのためこのイベントも職人さんが作る様子が見られるのがすごく面白い。子供に混じって10分ほど眺めていました
もちろん販売やお子さん向けのワークショップなどもあります。
車がある&作り手ならば足を伸ばして三木金物まつりもおすすめ
会期は11/2.3日の土日のみとなりますが、三木金物まつり もオススメです。姫路城から車で1時間弱かかります。
上記皮革フェスティバル見て、陶器市見て、菓子祭り見て、移動して金物まつりまで見ると確実に時間足りなくなるとは思いますけどね(;´∀`)
三木市は昔から金物=大工道具などが多い街でした。
秀吉が三木城主、別所長治との戦いで、寺も古い街並みも文化の足跡を焼き払い、町そのものが無くなりました。
しかし秀吉は、それ以後の三木のために大きな功績を残します。秀吉の復興事業が新しい三木づくりの原点となり、金物のまち三木は、この時から本格的に培われてきたとも言えるのです。復旧のため各地から大工職人が集まり、彼等に必要な大工道具をつくる鍛冶職人が増え、これが現在の発展につながる足がかりとなったのです。
三木金物の歴史より
あまり日本皮革産業連合会のblogで細かくこのイベントの解説すると怒られそうですので、下記blogでちょいと解説しています。道具工具好きは楽しめますよ。
彫刻刀屋が本気で作った革包丁は通常の革包丁とどう違うのか、という話。11/2.3は三木市金物まつりだよ。 | phoenix blog
11/16.17(土日) ひょうご皮革総合フェア2019&第28回たつの市皮革まつり
こちらも昨年紹介していますね。
毎年このイベントにあわせてバスを使ったタンナー見学会を行っています。皮革まつりを見て、タンナーさん2か所めぐりつつ私が解説する、というものです。(次回申し込みたい!というひとは「革日和メールマガジン」にまた登録していただくと連絡しますので。)
公式HP:たつの市/ひょうご皮革総合フェア2019&第28回たつの市皮革まつり
開催時期
- 令和元年11月16日(土曜日)9時30分~17時30分
- 令和元年11月17日(日曜日)8時30分~16時30分
開催場所
アクセス
公益財団法人童謡の里龍野文化振興財団 - たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール
車でお越しの場合 |
- 山陽自動車道「龍野IC」より西へ3分
- 国道2号太子・龍野バイパス「福田ランプ」より、国道179号を北へ約10分
- 国道2号太子・龍野バイパス「門前西交差点」を北へ約8分
- 中国自動車道「山崎IC」より、国道179号を南へ約40分
| 電車でお越しの場合 |
- JR姫新線「本竜野」駅下車、タクシーで約5分、または徒歩で約25分
- JR山陽本線「竜野」駅下車、タクシーで約15分
2018年の様子
今年のイベント内容紹介
下記サイトから抜粋しています。
公式HP:たつの市/ひょうご皮革総合フェア2019&第28回たつの市皮革まつり
ベストレザーニスト2019「俳優 速水もこみちさん」によるトークショー
 (写真:赤石仁)
(写真:赤石仁)
- 主催:一般社団法人日本皮革産業連合会
- 日時:令和元年11月16日(土曜日)13時から(開場12時30分)
- 会場:赤とんぼ文化ホール大ホール
※入場には入場券(全席指定)が必要です。当日午前9時から文化ホール建物東側壁面通路にて、先着順にて配布します。
レザーファッションショー(赤とんぼ文化ホール大ホール)

皮革を使って制作した衣装で、プリンセスたつのや高校生がモデルとなり、華やかなファッションショーを催します。
日時・出演
- 令和元年11月16日(土曜日)13時~14時20分(開場12時30分)
(11月16日のファッションショーはトークショーと連続して行いますので、入場券が必要です。)
出演:龍野北高校、2019プリンセスたつの、フラワープリンセスひょうご2019、姫路お城の女王、越部小学校、えびす - 令和年11月17日(日曜日)11時~12時10分(開場10時30分)
出演:龍野北高校、2019プリンセスたつの、フラワープリンセスひょうご2019、姫路お城の女王、龍野小学校、揖保小学校、西脇高校 - 令和元年11月17日(日曜日)13時30分~14時45分(開場13時)
出演:龍野北高校、2019プリンセスたつの、フラワープリンセスひょうご2019、姫路お城の女王、小宅小学校、西脇高校
皮革製品即売会(青少年館体育室、赤とんぼ文化ホール前屋外テント)
国産の天然皮革で作られた靴、カバン、ベルトなどの皮革製品を低価格で販売します。

皮革直売会、レザークラフト教室(青少年館ホール)
 地元、たつの市、姫路市のタンナーが製造した皮革素材や、製品をタンナー自らが販売します。また、ペンケースや小物入れが製作できるレザークラフト教室も開催。
地元、たつの市、姫路市のタンナーが製造した皮革素材や、製品をタンナー自らが販売します。また、ペンケースや小物入れが製作できるレザークラフト教室も開催。
革細工体験コーナー(赤とんぼ文化ホール大ホールホワイエ)
 たつの市産の天然皮革を使った動物革細工の制作体験コーナーを設けます。
たつの市産の天然皮革を使った動物革細工の制作体験コーナーを設けます。

学生による皮革作品の展示(赤とんぼ文化ホール中ホールホワイエ)
 上田安子服飾専門学校、神戸医療福祉専門学校三田校、神戸芸術工科大学の学生作品の展示をします。
上田安子服飾専門学校、神戸医療福祉専門学校三田校、神戸芸術工科大学の学生作品の展示をします。
ニューレザーコンテスト&表彰式(赤とんぼ文化ホール大ホールホワイエ)
 新素材開発、環境問題への対応など新時代にマッチした革のコンテストを部門ごとに行い、入賞した革の展示と表彰式を催します。
新素材開発、環境問題への対応など新時代にマッチした革のコンテストを部門ごとに行い、入賞した革の展示と表彰式を催します。
ニューレザーコンテストが面白い!11/16(土)なら解説します
個人的にはニューレザーコンテスト面白いです。
これはたつの市姫路市にあわせて130以上存在する各タンナーさんがテーマに沿った革を作ったものを競うコンテスト。「こんなの量産は到底無理だろ!」的な革も出ており非常に面白いです。
ただ、このコンテストですが、解説がないとさっぱり凄さがわかりません。またコンテスト上位に入るものは良くも悪くも「量産向き」「商売向き」な革が受賞する傾向にあります。それが悪い、とは言わないのですが、「これ、とんでもないだろ!」的なものは受賞しないものに数多くあります。あくまで、村木個人の感想ですよ(;´∀`)
あと、写真では手触りは伝わらないので実際に触らないと面白さはわかりません。
11/16(土)は私が11時半ごろからニューレザーコンテスト会場で15分ほどかけて「この革はこういう意図でこういう加工をしている」「この革はここが見どころ」などを解説しますので興味ある方は来てください。
当日バスの遅延などの可能性もありますのでfacebookで「~時からニューレザーコンテスト解説します」と書きますのでチェックしておいてくださいな。
FB: 村木 るい
ぶっちゃけ姫路城皮革フェスティバルとたつの市皮革まつり。どちらがオススメ?
どう書いても両方から恨みを買いそうですが、忌憚なく書いておきます。
姫路城皮革フェスティバル
陶器市や姫路菓子まつりが同時併設、かつ、姫路城近辺なのでお店や観光資源が豊富。姫路駅から徒歩圏内なのが良い点。
他方、材料を買うor革製品を買う、という視点で見るならば、たつの市皮革まつりのほうが多いです。素材は2つの組合が各タンナーさんから革を預かって販売されています。
たつの市皮革まつり
タンナーさんによる革素材の販売や、業者による革製品販売はこちらのほうが多いです。また、ニューレザーコンテストやレザーファッションショー、レザーニストトークショーなどもあります。
他方、アクセスという点で見るならば車がないときついかなぁ、と。JR姫新線本竜野駅西口と皮革まつり会場(千鳥ヶ浜駐車場)を結ぶシャトルバスが運行されていますので、車のないかたは是非それを使ってください。
参考リンク>たつの市/ひょうご皮革総合フェア2019&第28回たつの市皮革まつり
今後のムラキ予定
11/1.2.3 愛知県一宮 本日は革日和♪開催。セミナーや展示会しています
19.11/1.2.3 本日は革日和♪ in一宮 愛知県 にこういうものを持っていきます | phoenix blog
11/16 満席になってしまいましたがタンナー見学会です。次回参加希望の方はキャンセル待ちにご登録ください
2019たつの市皮革まつり&タンナー見学会 2019年11月16日(兵庫県) - こくちーずプロ
12/4.5 レザーフェアにてセミナー予定